令和6年度第2回綾瀬市社会教育委員会議(令和6年11月22日開催)
審議会等の名称
令和6年度第2回綾瀬市社会教育委員会議
開催日時
令和6年11月22日(金曜日)午前10時から正午まで
開催場所
綾瀬市役所 3階 312会議室
議題
(1)令和6年度神奈川県社会教育委員連絡協議会研修会代替について(動画視聴等)
(2)第56回関東甲信越静社会教育研究大会神奈川大会について
(3)令和9年度神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会(綾瀬市開催)について
出席者
委員
- (議長)澁谷 敏夫
- (副議長)増田 岩男
- 豊田 政治
- 長沼 康江
- 川村 和子
- 土田 章久
- 矢島 由美
傍聴者数
0人
内容
内容は、要点報告です。
議題(1)令和6年度神奈川県社会教育委員連絡協議会研修会代替について(動画視聴等)
議長:それでは、議題(1)令和6年度神奈川県社会教育委員連絡協議会研修会代替について、事務局は準備をお願いいたします。
事務局:(生涯学習課長より、令和6年度神奈川県社会教育委員連絡協議会研修会代替について説明・研修会動画視聴)
議長:では、本研修会の動画視聴を受けた感想や意見について、交換を行います。
私は、社会教育の良さは、「清く、正しく、美しく」といったイメージよりは、失敗から想像力を身に付けたり、成長していくイメージだと思っています。社会教育はそもそも、明治時代に日本が国民の知的レベルを上げるために、取り組み始めたもので、誰でもできるものでしたが、時代の変化に過敏に対応していった結果、現在のような敷居の高いものになってしまいました。また、社会教育委員会議は、来賓のなかで、市長、副市長、市議会議長に次いで並ぶほどの立場にあります。こういったことを言うと、「自分は偉い立場である」と主張するように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。それだけ重要な立場にあるということを委員の皆さんには理解したうえで、今後活動してもらいたいと思います。
議長:他に意見はありますか。
(意見なし)
議長:他に御意見・御質問がないようですので、続いて、議題(2)に移ります。事務局から説明をお願いいたします。
議題(2)第56回関東甲信越静社会教育研究大会神奈川大会について
議長:それでは、続いて議題(2)第56回関東甲信越静社会教育研究大会神奈川大会について、事務局より説明をお願いいたします。
事務局:(前回会議での決定事項についての確認、現在の進捗状況について説明。)
議長:事務局の説明が終わりました。事務局の説明に補足しますと、前回会議まで、本大会の大学生の参加費は大学生自身が負担するということになっていましたが、現在、事務局にて大学の方で負担できないか検討しているとのことでした。現在の事務局案で、進めて良いでしょうか。
(全員承認)
議長:では、事務局はこのまま進めてください。続いて、議題(3)について、事務局から説明をお願いいたします。
議題(3)令和9年度神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会(綾瀬市開催)について
議長:それでは、続いて議題(3)令和9年度神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会(綾瀬市開催)について、事務局より説明をお願いいたします。
事務局:(過去本市において開催した地区研究会について、令和5年度、令和6年度に開催した地区研究会の概要について説明。)
委員:今月2日に参加した海老名市での地区研究会では、社会教育委員と地域の方との「横のつながり」があると感じました。他の市町村での内容を聞くに、発表2~3年は準備をする必要があるのではないかと思います。その際に綾瀬市の社会教育委員も地域との「横のつながり」を持てれば良いのではないかと思いました。
議長:そういった地域活動を実際にされている方が社会教育委員にいれば、「横のつながり」も作りやすいのだと思います。例えば、学校での取り組みの紹介等がそれにあたると思いますが、先日聞いた小学校の授業での子どもたちの発表はとても良かったです。
委員:地域コーディネーターや市職員の協力等もあり、学校でも地域と関わりを持っています。
議長:我々が知らないような、市内の工場やお店を細かく調査しており、しかもそれを小学校3年生がしているということに、とても感心しました。この間の海老名市での地区研究会で、共に参加した委員と話していたのですが、定例会とは別に、任意参加でこういった好事例や社会教育について勉強する機会を設けたいと思いました。皆さんの意見はいかがでしょうか。
(賛成意見多数)
議長:実は、前回の綾瀬市での地区研究会は評判があまり良くありませんでした。内容自体はとても良かったと思いますが、「市長・教育長が他公務により欠席」という他の市町村ではあまりない事態が起きてしまったためです。令和9年度に開催する地区研究会では「小さい市でもしっかり社会教育に取り組んでいる」と思ってもらえるように取り組みたいと思っています。そのためにも、テーマ設定等含め、勉強会を開催できればと思います。
委員:しばらくの勉強会のテーマは、令和9年度の綾瀬市での地区研究会の発表内容をどうするかということになると思います。
議長:ペースとしては、定例会のほか2回ほどの開催ということでいかがでしょうか。
委員:季節ごとの年4回に開催してはいかがでしょうか。
(賛成意見多数)
事務局:季節ごとに年4回開催するとして、委員の皆さんの日程調整の負担を考慮すると、うち3回は定例会後に開催する方が良いでしょうか、それとも別途日程を組んだ方が良いでしょうか。
全体:事前に決まっている方が良いため、定例会後の開催の方が良いです。
議長:では、その方向で取り組んでいきましょう。本題に戻します。海老名市での地区研究会はどうでしたか。
委員:海老名市では、80歳の日本舞踊家が社会教育委員を務めていらっしゃっていて、実際に現役で小学校に出向いて指導していると聞いて驚きました。OBやOGでない現役の方が社会教育委員として活動されているという点で良いと思いました。また、発表内容も地区研究会のために用意したものではなく、学校・地域に社会教育がうまく溶け込んでいるような既存の活動の発表というところが良いと感じました。おそらくですが、綾瀬市にはなかなかないのではないでしょうか。
議長:綾瀬市の社会教育委員会議にも、現役で子どもたちと関わっている委員がいます。良い機会ですので、難しい話になりますが、教育について振り返らせてください。教育には、社会教育と家庭教育と学校教育があります。そのなかでも社会教育は学校教育(一部除く)と家庭教育を含む大きなものです。ただ、実際のところ、家庭教育は各家庭で行われるものであり、介入することが難しいです。子どもに悪いところがあった際、よく「親が悪い」と言いますが、その「親」を育てた「親」も悪くなります。また、社会教育は、「学習」ではなく「教育」です。人が生きていくうえで自然と覚えるといった「学習」ではなく、高校・大学受験で必要となるような資格が「教育」にあたります。この「教育」といった言い回しが「偉そうに聞こえるから」と文部科学省が、社会教育課を生涯学習課へ名称を変更した経緯がありますが、「学習」という広い範囲の言葉を使った結果、狭義での「生涯学習」を行うしかなくなってしまいました。「社会教育」という言葉にはこういった経緯があります。他にもわからないことがあったら、ぜひ聞いてほしいと思います。
委員:委員の選出区分に実は疑問を持っています。現在「市民公募」といった枠で活動をしていますが、この枠はどういったものなのでしょうか。
事務局:(社会教育委員の選出区分について説明)
委員:私の選出区分について、理解しました。
情報交換
事務局:((1)令和6年度綾瀬市社会教育委員活動経過及び今後の予定について、(2)令和6年度教育委員会における事務の点検・評価について、(3)綾瀬市図書館基本構想(案)の意見募集(パブリックコメント手続)について、(4)中学校部活動の地域移行について、説明)
議長:ただいま、事務局より報告がございました情報交換について、質問や意見等がございましたら、発言をお願いいたします。また、令和6年度綾瀬市社会教育委員活動経過について、直近の9月~11月に開催いたしました県社会教育委員連絡協議会等にて得た学び等がありましたら、御報告をお願いいたします。
委員:部活動の地域移行に際し、資料(リーフレット「綾瀬市立中学校の部活動の地域移行について(第2版)(PDFファイル:683.3KB))では「子どもファースト」という言葉が用いられています。この言葉自体は良いと思いますが、廃部にしたり、受益者負担になったりする等、実際のところ部活動を地域に移行して得られるメリットは大人向けであり、「子どもファースト」という言葉からは離れているように感じます。現在も家庭の経済的な理由で、部活への参加を諦めてしまったり、入部してもユニフォームが買えなかったり、交通費が払えないから大会に参加できない子どもたちがいます。そのようななかで、受益者負担の事業を進めていくということですが、家庭の負担がないようにしてほしいです。
また、資料に地域クラブの指導者募集について記載がありましたが、指導者の募集について、ホームページには掲載されているのでしょうか。
事務局:掲載されていません。
委員:他市では、ホームページに部活動指導者の雇用条件等が要項として掲載されているところもあります。そういったところで示した方が、市に直接問い合わせをするよりも簡単に確認ができて良いのではないでしょうか。また、正直なところ、この事業については、現状を見ないで進めているような、先走っている印象があります。こういった意見があったことは把握しておいてほしいです。
議長:大変重要な意見だと思います。この他に何かございますでしょうか。
委員:10月18日の社会教育委員連絡会議に出席した際の報告をいたします。会議では、声なき声を聴くことに大切さについて話を聞きました。県央教育事務所の指導課長が、「不登校は子どもの甘えではなく、『行きたくない』環境を作っている学校の問題である。そんな不登校の子には『なにかとつながりたい。けど切られるのが怖くて言えない』といった声にならない声があった。」と話していました。また、講演では、講師の公民館での勤務時のエピソードとして、仲良くなった利用者の様子がおかしくても(利用時間・頻度が高すぎても)、職員として特別扱いをすることができずにとても悔やんだというものがありました。この聴こえない「声」を持つ人に今後どう関わっていくかが重要ではないかと思いました。
議長:そういった正解がわからない、矛盾しているような話はいくつもあると思います。先ほど述べられていた公民館の例だと、どんなに利用者と仲良くなっても、館長として守らなければいけないことは、「公共施設を個人のものとして使用されるのは困る」といった姿勢です。子どもを例に挙げると、子どもは常に動き回るものですが、学校では「席から動いてはいけない」と子どものために指導します。違う立場からの両輪の姿勢、ある程度のところで折り合いをつけることが大切だと思います。また、こういった矛盾したことは、その時に正解はなく、後から「この方法が最善だった」とわかるものです。その難しさを知ったうえで判断する必要があると思います。また、その判断をするのは専門的な知識を持ったうえで、行政が行います。事務局から先ほど説明があった、部活動の地域移行についてもそうですが、経済的な問題があっても、本当の意味で「子どもファースト」が叶えられていなくても、現実を見て実際にできることを行っていく必要があると思います。図書館の再整備については、莫大なお金が必要となります。そんななか、どんな図書館が良いかと市民に聞けば、「今よりももっと良い図書館を!」とあれもこれもと望む声が出てきますが、お金には限りがあり、すべてを叶えることは不可能です。ただ、建てる前に最善の策をわかっている人物もいないため、とりあえずどんな意見でも多くを出すことは重要だと思います。その際にぶつかり合いがあっても良いと思います。今、綾瀬市は公共施設の建て替え時期が一気に来ており、深刻な財源不足に直面しています。お金がないなかで、建て替えをどう行っていくのか、この決断を行うのは行政です。そして、社会教育委員は、そういった難しさについて、片方の立場に寄った断片的な意見ではなく、様々な立場のそれぞれの意見を誤解のないように、市民に伝えていくことが重要な役割です。「みんなで考える」とよく言いますが、実際に考えるのは個人です。その個人の考えをぶつけ合うことで、一つの意見に絞っていくことが本当の社会教育です。社会教育委員という地位を持っていることを自覚して、断片的なことを言って市民に誤解を与えないようにするためにも、皆で話し合う会議の場が必要になるのです。
議長:この他に、全体を通して何かございますでしょうか。
議長:情報交換(3)の図書館について、今の図書館は、本を入れておく倉庫のような状態であると思います。開館した当時は良かったと思いますが、今の時代の流れにあった変化が必要です。知人は、子どもがお腹一杯の時に食べ物を残しているところを見て、「残すのは良くない」と言っていましたが、今の時代、その残飯を使って飼料や肥料にして商売をする人もおり、「無理に食べろ」という時代ではありません。そういった時代の変化にも敏感になる必要があると思います。
議長:この他に何かございますでしょうか。
(意見なし)
議長:以上で提出された議題は全て終わりました。事務局に進行をお返しします。
事務局:議長、ありがとうございました。それでは、副議長、閉会挨拶をお願いいたします。
副議長:私は、ずっと社会教育委員会議として何かをやりたいと思っていました。皆さんは個人でそれぞれ様々な活動をされていますが、会議としてはあまり取り組めていないと感じていたためです。そんななか、今日の会議で「定例会以外に年に4回ほど社会教育について自由に話す機会を設けたい」という意見が出て、とても嬉しく思いました。社会教育に関連した取り組みについて、地域学校協働活動について紹介させてください。これは、「学校を地域の力で充実させていこう」という取り組みで、私は綾南小学校の地域コーディネーターをしています。活動内容のひとつに「朝の校庭の見守り」があります。始業前、教員は子どもたちが怪我をしないか、校内に不審者が侵入してこないかと心配をしていますが、始業前は特にとても忙しく、外まで見回りをする余裕はありません。そういった学校の悩みに対応して見守りを始めました。見守りをするにあたって、事故・トラブルになりそうな時以外は、子どもたちの成長のために干渉せず、子どもたち自身に任せるように心がけています。こういった取り組みが、社会教育委員の皆さんの近所の学校でもあると思いますので、ぜひ取り組んでいただければと思います。また、こういった活動を社会教育委員会議として、取り組んでいければと思います。それではこれにて、第2回社会教育委員会議を終わります。
以 上
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


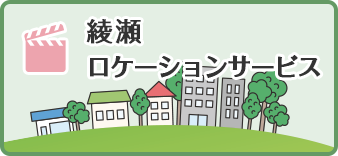
更新日:2024年11月29日