令和6年度第1回綾瀬市総合計画外部評価委員会(令和6年7月5日開催)
審議会等の名称
令和6年度第1回綾瀬市総合計画外部評価委員会
開催日時
令和6年7月5日 13時30分から16時30分
開催場所
綾瀬市役所 3階 314会議室
議題
外部評価
- (支える3)大規模自然災害対策プロジェクト
- (支える4)誰もが便利な移動手段強化プロジェクト
出席者
(委員8名)羽田委員長、諸坂委員、丸山委員、吉原委員、鈴木委員、平出委員、井上委員、立花委員
(主管課)危機管理監兼危機管理課長 他2名、都市整備課長 他1名、福祉総務課長 他1名
(事務局)企画課長 他2名
傍聴者数
なし
内容
内容は要点報告です。
〈支える3 大規模自然災害対策プロジェクト〉
(主管課より資料に基づきプロジェクト概要及び一次評価結果を説明。企画課より二次評価結果を説明。)
地域の防災・減災力の向上:委員評価 B
委員長:「地域の防災・減災力の向上」について、主管課と企画課の評価にあるように、委員会としての評価はBでよいか。ただし、これはステップ1「市民等への防災意識啓発の強化」及びステップ2「担い手の拡充」をあわせて相対的に見たときの評価である。「担い手の拡充」については、地域防災リーダーについてや、地域防災の担い手の育成・拡充と教育の体制づくりについて課題がある。これについてはきちんと今後対応していただきたいということをお願いする。地域防災リーダーについては、役割が明確化されていないため義務の明確化が必要であるということが課題として挙げられている。そもそも地域防災リーダーとは何か、整理して取りまとめたものはないか。公募等で地域防災リーダーを依頼しているのではないのか。
委員:私は自治会の立場で危機管理課と防災に関わってきた。地域防災リーダーは、以前、担い手の育成の一環として自治会の各区から数名選出していた。10年以上経過するが、これが順調にいかず、3年か4年ほど前に、早急に地域防災リーダーを作ろうということになった。防災について自治会は多くの関わりがあるが、自治会に加入していない一般市民については全く見えてこない。今後の課題としては、自治会に加入していない人をどれだけ巻き込むかが重要。市だけでなく、会社でも避難所等いろいろ備えている。それが見えるようになると非常によいと思う。主管課の取組は評価したい。
危機管理課:委員から話があったとおり、市内の14自治会ごとに地域防災リーダーがいる。地域の温度差は非常にあると思う。地域防災リーダーは地域の防災力を上げようというところから発足した。各自治会に任せている部分もあるので、自治会によりリーダーをどう活用していくかという課題がある。また、市としても今まではっきりと示してこなかった課題もあると思っている。今年度から地域の避難所開設訓練は、市の総合防災訓練とは切り離し、災害発生時に中核となる市役所がどう地域と連携して上手く対処していけるのか、市役所の内部の体制について一番に取り組む。地域の避難所運営は訓練を続けてきておりノウハウを持っている。それに加えて地域防災リーダーや自治会が中心になると思うが、誰が避難所に来てもすぐ避難所開設できるよう施策を行っている。地域と災害対策本部の両輪で取り組んでいかないと大災害は乗り越えられない。いろいろなご意見をいただきながら、しっかりと対策していかなければいけない。すぐに答えは出ないが、何かしら手を打っていかなければいけない、一歩ずつでも進んでいかないといけないと考えている。
委員長:自治会の加入率が低下している中で、先ほど委員が話したように、自治会に加入していない市民への意識啓発、防災活動への巻き込みをどうするかということは大きな課題だ。この辺りはステップ3「新たな地域防災の仕組みづくり」に関する話かとも思うが。これを意識して引き続き取り組んでいただくということで、まとめさせていただきたい。
委員:ハザードマップは非常に充実した内容で、安全対策や避難行動のポイントが掲載されており、二次元コードを読み取ると川の氾濫状況を見ることもでき、地域の情報が多くすばらしいと思う。小中学校との連携について、防災教育に取り組んでいるが、消防署見学やAEDの体験等も行っており、防災教育の推進を協力して取り組めていると実感がある。課題については、防災倉庫があるにも関わらず、備蓄するスペースが少ないという点やベッドの数が少ない点は、早急に対応していただきたいと感じている。そのためB評価が妥当ではないか。
委員:災害時にどうしたらいいか知らないという、近隣の高齢者の話をよく聞く。歩いて避難できないから支援がほしいという登録名簿のことは私も知っているが、実際は実施されているのか。
委員:避難所登録という、本人の了解を得て、そうした人を助ける仕組みはもうできているそうだ。一人暮らしの高齢者や障がい者を支援する取組は正式にあるだろう。
危機管理課:それは個別避難計画という。
委員:そこに全部登録されていて、そういう支援をする組織はできている。自治会に入っていればすぐに情報が伝わるが、加入していない方は回覧が回らない。広報等に掲載されていても理解しにくいことがある。会員であろうと非会員であろうと情報が伝わるようにしないといけない。情報伝達でいえば、今は外国人市民のこともある。
委員:個人情報は保護しないといけないが同時に、利活用しないといけないもので、法律に、個人情報を活用して国民生活の公益に資すると書いてある。
委員長:一般市民への普及啓発、情報提供、さらに進んで防災対策の活動への参画をどう促進するかはやはり大きな政策課題だろう。意見として市にお願いする。
委員:防災訓練の参加人数について、1年間で1000人はやはり少ないのではないか。自治会の会員はすでに対応を分かっているから、対応を分かっていない人が訓練しないといけない。分かっていない人に、市がどれだけのことをやるかがこれからの課題だ。自助、共助、公助の中で、共助が大切だというが、共助とはどうすればよいかが分からない。結局「公助」として「共助」をサポートしないとコミュニティや自治会により考え方がバラバラになる。公助という形で市から発信して、共助のボトムアップを図り、さらに市民一人一人に自助の意識啓発や意識改革をしていかないといけない。だから市役所がサポートしないと、綾瀬市に限らず、共助はなかなか進まないのが現状だ。一方で、携帯の充電器などの整備は自助の範囲。被災地では、市が大容量のバッテリーを用意して、避難者がコンセントを挿して好きな時に充電すればいい。自助と共助と公助について、どこまで共助で、どこまで自助かという議論をきちんとしているのか。命を守るためのサービスと快適な生活を営むためのサービスはやはり次元が違う。市民に対して正しい情報を提供し、市民の意識啓発をいかに市が推進するか、この委員会の附帯意見として付けたほうがいいのではないか。
復旧・復興対策の充実:委員評価 C
委員:今年度の取り組み予定一つ一つはすべて重要であるため、確実に進行していただきたい。緊急度の順番に関して、公共政策の分野では、ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(以下、WBS)というものがある。そのような今後の設計や進行表を作成しているか。
危機管理課:WBSのようなシステマチックな業務管理優先度の表はないが、本年度の取組予定の中の「復旧・復興対策の充実」のステップ1「復旧・復興対策の整備」にあるように、地域防災計画などの防災関連計画の根本的な見直しができておらず、庁内体制も災害時に速やかに対応できる状態になっていないということを、一番緊急度の高い課題として本年度に位置付けている。
委員長:取り組みの方向「復旧・復興対策の充実」については、主管課、企画課とも に、ステップ1「復旧・復興体制の整備」はC評価、ステップ2「円滑な復旧・復興体制の構築」もC評価となっている。外部評価委員会としての評価もCでよいのではないか。委員から緊急度の順番も考慮しスケジューリングを大切にしていただきたいという意見があった。他の意見はどうか。私はステップ2の主管課の課題認識は極めて重大な認識だと思っている。課題への対応に、業務委託で受援計画を策定するとあるが、委託先の外部の事業者は知識やノウハウがあるのか、綾瀬市の立場に立っての受援計画を策定できるのか。
危機管理課:計画の内容の見直しは市の職員が行う。外部委託先の事業者は、受援計画で市が決めるべきことや記載が漏れてしまっている事項、効率化のための改善点などを市にアドバイスし、行政自身が計画の策定を行う。
委員:復旧と復興はワンセットでよく言われるが、復旧とは、いわゆるライフラインの復旧など、1日も早くしないといけない。国や自衛隊の支援も入れて、とにかく1日も早く復旧することがポイントだ。復興とは、住民の意向を確認しながら、もう一度まちを再生することだから、住民参加が非常に重要なポイント。復旧と復興は実は全く違う。復旧の協力体制について、例えば、非常時にSOSを綾瀬市長が発信して、何時間以内には県や自衛隊が到着するような連携を構築しておくとよいと思う。それはもう議論しているのか。
危機管理課:いま指摘された件がまさしく受援計画となる。どこのセクションがどこの関係機関へコンタクトしてどのように行うかという仕組みがないことが一番の弱点だと考えている。そこを受援計画の策定で埋めていきたい。
委員:市だけで重機を持って現場に出ることはまず不可能。ドローンの使用や自衛隊の要請をどれだけ迅速に漏れなく展開できるかが一番命を守る施策として重要と思う。まずはそうした受援計画に取り組むということで承知した。
委員:災害時はどのような考えで基地を活用するのか。取組の交渉等は行っているか。
危機管理課:厚木基地の米軍の危機管理セクションとは、意思の疎通を図り、どのような相互支援ができるかという協定がある。海上自衛隊とは覚書がある。いずれにしても、災害が起きたときのパイプ、チャンネルはつないでおこうという基本的な枠組みはある。具体的にどうするかは今、検討しているところだ。
また、広域搬送医療というものがある。綾瀬市内の病院が被災した際には近隣市に搬送することになるが、道路が使用できない場合もあるので、厚木基地が神奈川県のSCU(航空搬送拠点臨時医療施設)という災害時の拠点になっている。綾瀬から救急車で拠点まで搬送して、そこから飛行機で他県の病院に搬送する。逆に地方が被災して神奈川県に受け入れを依頼された場合には、その拠点から綾瀬の救急車で近隣病院まで搬送するという体制もある。
委員:災害がいつ起きるか分からない。危機管理課の資料の中に、学校との連携という言葉が出てくる。企業は、工業団地がいくつかあり、昼であればそれなりに人がいる。工業団地はそれなりの体制や組織を持っているはずだ。それをいかに危機管理課として統括するかになるのだろうと思うけれども、昼に地域にいる人たちの中に、元気な人はいないだろう。そうすると、一番力になるのは中学生だろうか。エネルギーがあり、非常に能力のある彼らが、もっと有効活用するような危機管理課として指導等があってもよいのではないかと感じる。
委員:数日前のニュースで、高校生がドローン操作を消防から教わり、災害時には、高校生がドローンを操作して救援物資を避難所になっている高校に運ぶということを報道していた。子どもたちに危険な仕事はさせられないけれども、可能な限り協力をしてもらう。高齢者の支援や物資を運ぶドローンの操作など、市と教育委員会でタイアップすることは不可能ではない。
危機管理課:中学校で防災講座として講話をしたり、消防署から救急訓練をしたりしている。過去の災害事例でも、避難所で子どもたちの明るい声を聴いて大人が前向きになるということはある。
委員:中学生が、小学校に兄弟がいる場合は迎えに行ったり、そういうこともしているはずだ。
委員:それは行われている。また、AEDの体験は本当に意味がある。中学生も実際に体験することで、いざというときに動けると思う。実際の本番の時にどれだけ気を配れるか、日頃から教育していくことも大切。
危機管理課:心肺蘇生法とAEDについては、消防でも裾野を広げるような形で取り組む。まずは知識を持っていただき、その知識を実際の現場でどう使えるかが最終的なところ。
委員長:外部評価委員会として、この「復旧・復興対策の充実」に関しては、進捗状況の評価はCということで、主管課の一次評価に書かれている課題認識、今後の課題への対応も妥当であろう。ただ、今後の課題への対応に関しては、各委員からありましたように、企画課による二次評価に書かれている、庁内全体の災害対応力の向上に取り組む、これは当然であろう。それに加えて、企画課の二次評価に書かれている、非常時にきちんと機能するよう他の自治体関係事業者等との連携をとり、と書かれているが、先ほどの、庁内全体の災害対応力の向上はもちろん市内の学校、団体、他の自治体関係事業者に加えて、関係機関等との連携を取り、というようにこの辺りの課題を解決していただきたい。
〈支える4 誰もが便利な移動手段強化プロジェクト〉
(主管課より資料に基づきプロジェクト概要及び一次評価結果を説明。企画課より二次評価結果を説明。)
公共交通の利便性向上:委員評価 B
委員:コミュニティバスと路線バスの運賃格差に不満があるという課題について、これは路線バスを利用する高齢者からの不満か。
都市整備課:そのとおり。コミュニティバスは一部の地域のみ運行している。路線バスの方が運賃は高いため、コミュニティバスを利用できない地域から不満の意見がある。
委員:対応として路線バスの補助が挙がっているが、この補助は高齢者限定か。
都市整備課:運賃については公共交通事業者との調整や意見交換も必要になるが、将来的には、まずコミュニティバスの再編の中で、コミュニティバスを利用できない地域の方との格差や負担を公平にできないか検討している。具体的な方法は未定。コミュニティバスの現在の運賃は、一般の方が180円、65歳以上の高齢者は100円としている。路線バス各社も高齢者割引を実施しているが、対象年齢がもう少し高い、あるいは定期券のような期間付きパスを購入して100円で乗れる仕組み。そうした部分について、公平にできるような助成制度を今後調整していきたい。
委員:高齢になると今までできたことが全てできないことに変わってしまう。元気な頃は見晴らしがよい高台に住み、高齢になって坂道を登れないということが起きたとき、私たちはそこから移ればいいと思うが、それができない。これから、例えばバス路線の変更もおそらく10年20年かかる話ではないかと思っている。会社経営者からすると、これは生産性の問題だと置き換えられる。会社なら、生産性がよく生活しやすい場所はどこかというように探すと思う。だから、綾瀬市もそういう考え方にチェンジしていくまちづくりができないかと思っている。私が考えたことは、チェーン店を呼ぶのではなく、地元の商店も病院も中心市街地に集めて、そこに皆が集まるようにバス路線も配置する。保健福祉プラザ、病院、商店、市役所が全部1か所にあれば、皆が楽になるのではと思っている。そして、ある一定の年齢層の方はバス路線の辺りに住んでいただく。土地等いろいろな問題があると思うけれども。皆に公平にすることは無理だと思う。私が疑問に思うのは、高齢者の運転がなぜ問題か。ブレーキとアクセルを間違えるというが、それならば高齢者が自動ブレーキ機能付き自動車に乗れるよう補助金を出せないだろうかと考えている。高齢で歩けないから車に乗りたいのに、車を取り上げて歩きなさい、これでは問題は解決しないと思う。高齢者がブレーキを間違えても止まれる自動車への補助金を用意するという政策はどうだろうか。高齢者もずっと車に乗っていられるまちというイメージができるのではないか。
都市整備課:いわゆる公共施設等を利便性の高い基幹的な道路沿いに集約して、皆さんが移動をしなくてもよい、自動車に頼らず生活できる集約型の都市づくりを都市マスタープランで目指している。委員から話があったとおり、移動しなくてよいまちづくりを進めるところもあれば、全てがすぐにそうならないという状況の中で、高齢者の移動に対してどういった支援ができるのか。都市整備課では、既存の公共交通の事業者や、自動運転等の新技術などを取り入れながら、移動の支援について進めている。委員が話していた、安全運転の新技術への補助や助成は、綾瀬市だけでなく、国や県も、いろいろなところで考えていかなければならない。全員に公共交通や移動支援だけで対応するのは非常に難しいと課題として認識している。少しでもそうした不便を感じている方々のために、少しでも利便性の向上を図れるような取り組みを進めていきたい。
委員:対象者の行動パターンを集約できているか。いわゆる最大公約数はどこか調べると、コミュニティバスのまわる場所は決められるのではないか。
都市整備課:具体的にどのような動きをしているか、アンケート調査をした。コミュニティバスの利用目的について質問したところ、高齢者の回答が多いのは買い物や病院、公共施設への移動であった。そうしたところへの移動支援が必要。
委員:小園から保健福祉プラザまで乗り換えないといけないことはとても不満。それを一番切実に願っている。基本的なまちづくりがいかに大事かと思う。
都市整備課:今は市の中心部、市役所ロータリーが交通の結節点という形で運行しているが、市役所から保健福祉プラザへの移動については不足しているということは課題として認識している。保健福祉プラザをすぐに移転するという対応は難しいため、保健福祉プラザへの移動が便利になるようにバスの再編という形で取り組んでいきたい。
委員長:委員の指摘は、より長期的な綾瀬のまちづくりの都市計画の中で公共交通をどう整備していくのかという指摘で、おそらくステップ3「利便性向上の仕組みづくり」に関わってくる話ではないかと思う。ステップ3は、より大きく綾瀬全体の都市づくり、都市計画の在り様を絡めて考えていくことが大切なのだと思う。今回の評価として、公共交通の利便性向上の一番基礎的な部分で、現状の公共交通の検証、特にコミュニティバス運行の見直しについてどう考えるべきか。主管課による課題認識については、先ほどの指摘は長期的な話として、今日の段階でのここのステップ1の進捗状況はB評価。主管課による課題認識は適正と思う。
複合的な交通手段の展開:委員評価 B
委員:御殿場アウトレット行きのリムジンバスを利用したとき、乗車していたのは2人のみ。リムジンバスの誘導は羽田空港へのアクセスを考えていると思うが、渋滞の心配もあり、無理して取り組まなくても、誘導が困難な状況というのは仕方ないように感じる。課題への対応について、自動運転やAIデマンド交通等はまだなじみが薄く、これからのものと感じる。シェアサイクルについては、民間等でもう取組を行っているようなので、例えば、免許返納したが自転車はまだ乗れるという高齢者のために、三輪など工夫して買い物や病院、公共交通、公共施設などに行けるような取組をするとよいのではないか。
委員:保育所の送迎は電動自転車を利用している方が多い。高齢者が自転車で移動するなら補助も良いと思う。坂が多い地域だから電動自転車はありがたい。
都市整備課:シェアサイクルについては、今、事業者と導入実証実験に向けて調整している。シェアサイクルは駅に利用需要があり、綾瀬市は鉄道の駅がないので単独の導入が難しい。近隣自治体で昨年、一昨年から実証実験が徐々に始まり、ようやく綾瀬市から近隣の駅に向かうシェアサイクルの整備をできる環境が整った。今後、実証実験の導入を進めていきたい。
委員長:「複合的な交通手段の展開」の取り組みの方向について、主管課はB評価、企画課がC評価としている。これは内容的にBともCとも言えないのではないか。各委員からの意見にも特にこの点で評価に関する意見もなかったので、主管課による評価を尊重し、当委員会としてB評価とする。課題認識については、主管課の課題認識、課題への対応でよいと思う。これも各委員からシェアサイクルなどの話もあり、企画課の評価の中にもあるように、総合計画を策定したときから社会環境も変化してきているので、新たな交通手段導入についてはさらに、一層調査研究を進めていただきたいということを委員会の結論とする。
地域における移動手段の充実:委員評価 B
委員:綾西団地の高齢者の買い物などの交通手段として資料にあった小型バスは、どういう仕組みか。
福祉総務課:住民のボランティアで運行している高齢者の移動支援だ。市で購入した公用車を、ボランティア団体の利用時に貸し出している。自治体により方法は様々だが、綾瀬市の場合は、住民がボランティア団体を立ち上げ、市は事業促進のため、団体の経費負担軽減として公用車を貸し出している。利用者の負担は、基本的に謝礼程度までという仕組み。
委員長:「地域における移動手段の充実」について、主管課、企画課ともに評価はBとしている。質問が特にないため、当委員会としてはB評価とする。それから課題認識については、主管課の認識で適正である。今後は、資料に書かれている課題への対応をしっかり行っていただきたいと要望したい。
委員:ステップ2「取り組みの展開・拡大」の課題への対応について、社協等との連携と書かれており、私も絡んでいる件のため、ともにいろいろな意見を出し合い、行政と協力して取り組んでいきたい。
委員長:主管課の課題への対応には「社協等、他機関との連携による地域団体へのヒアリングを行い」と、企画課でも「団体への支援を行うとともに」とあり、しっかり課題として認識しているので引き続き頑張っていただきたいと、当委員会としてお願いする。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 企画課 政策経営担当
電話番号:0467-70-5635
ファクス番号:0467-70-5701
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


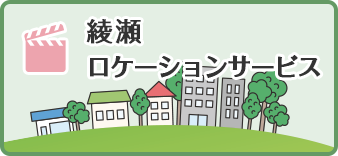
更新日:2024年10月25日