令和6年度第2回綾瀬市総合計画外部評価委員会(令和6年7月23日開催)
審議会等の名称
令和6年度第2回綾瀬市総合計画外部評価委員会
開催日時
令和6年7月23日 13時30分から16時30分
開催場所
綾瀬市役所 1階 J1-1会議室
議題
外部評価
- (育てる2)外国人市民が活躍する多文化共生のまちづくりプロジェクト
- (稼ぐ2)あやせ工場プロジェクト
出席者
(委員7名)羽田委員長、池田晋平委員、丸山委員、鈴木委員、平出委員、井上委員、立花委員
(主管課)市民活動推進課長 他1名、商業観光課主幹、工業振興企業誘致課長 他1名
(事務局)企画課長 他2名
傍聴者数
なし
内容
内容は要点報告です。
稼ぐ2 あやせ工場プロジェクト
(主管課より資料に基づきプロジェクト概要及び一次評価結果を説明。企画課より二次評価結果を説明)
技術力の向上に向けた支援:委員評価 B
委員:なぜ全てB評価なのか。計画の中で、まだ当初段階だからB評価なのか、1年間実施した中でB評価なのか。私はAと評価していいと感じているが、実際、主管課と企画課はどのように感じているか。
委員長:本委員会で拝見する限り、それなりに取り組んできているが、まだ課題が残っていることからBと評価しているように思う。その点はいかがか。
工業振興企業誘致課:当課としては、幅広く多角的な視点で中小企業支援を展開しているが、さらに一段二段上げられる伸びしろがあると認識している。しっかり積み上げながらAを目指していきたいので、今回はBと評価している。
委員長:サポートする側の行政側はまだ伸びしろがあると認識している。現場の立場からは、すでに伸びきっているという認識はあるのか。
委員:現場としても伸びしろがあると認識している。今回、みなB評価やC評価で、それほど進んでいないと感じる。取り組んだことは評価しないと周囲ががんばれなくなるので、過大評価かもしれないがA評価にするという意見があってもいい。一緒に参加している私たちとしては、プロジェクトの到達点があることも分かるが、この事業はA評価だという声を聞きたい。
委員長:あやせ工場プロジェクトの取組は、県内でもがんばって取り組んでいる方だと思っている。来年以降はBからAに評価が上がるのではないかと見ているが、その辺りはいかがか。
委員:もう少し評価していいのではないかと思う。ステップ3の段階ではおそらく変わっていくと思う。私も十数年前までものづくりに携わってきたから、主管課は謙虚に評価していると思う。
委員長:企画課による二次評価は、主管課による一次評価をさらに簡潔にまとめられていて、ほとんど主管課と企画課の認識は同じだろう。
委員:小学生が近隣の工場見学をして非常に驚いている部分もある。受け入れ体制も大変親切に対応しているので、将来の種をまいて実を結ぶように、さらに努力をお願いしたい。
委員:高校生が地元の工場見学や体験させてもらえるような取組はないか。
委員:実際オープンファクトリーには高校生は来ない。オープンファクトリー開催のきっかけは、小学生が10年後、地元の企業に入るきっかけをつくりたいということ。工業団地は危ないから入ってはいけない場所と一般の人に思われている。そこに大きな垣根を感じ、まず小学生に工場見学をしている。普段見たことがないものを見たい、危ないと言われると余計に見たいという気持ちが人間の心理としてあると思うので、工場側が安全をよく考えた上で内部を見せることは可能だろうと思い、開催した。高校生はどちらかというと、就職という目の前の目標があり、なかなか見にきてくれないのではないかというところがあり、まずは小学生から始めた。ようやく学年で工場見学したり、校長会で話を聞いていただいたりした。今の小学生が高校生になったとき、今とは違った状況になると想像している。
工業振興企業誘致課:高校生に関しては、独自の予算をかけない事業で、近隣の高校24校に対してアプローチし、就職を考えている高校生に市内企業を見てもらう取組を行う予定。就職という切り口だが、昨年は2校から2名が就職したという実績が出ている。高校生には別のアプローチをしている。
委員:市内企業への手厚いサポートに感動した。今は種まきの時期で、芽が出るまではまだまだ時間がかかると思う。ただ、高校生2人でも就職につながったことはすごく大きいと思っている。今後、この「技術力の向上に向けた支援」の取組として、どういうふうなスパンで、具体的な目標を立てているか。ステップ3「あやせ工場の企業力強化」はこれからというところだが、具体的な指標はあるか。
工業振興企業誘致課:ステップ3の達成に向けて、共同受注体制に到達するには、共同受注するためのファシリテーターがいないと難しい。市内企業のいろいろな強みをまとめ上げる力をもつ人がいないと、なかなか共同受注は難しい。もう少し時間がかかると考えている。いつぐらいまでかについては、基本的には実施計画という動きの中で、KPIを3年で構成している。そこに関しては、新分野への挑戦のほか、今は人手不足という大きな課題があり、その対策として機械化、自動化、省力化、省人化というキーワードが出てきているので、企業としてもそこに注力するところ。人の確保と機械化、両方ともいろいろなアプローチで支援している。「技術力の向上に向けた支援」の中では、設備投資について強力に支援し、省人化も狙いながら、新しい分野や新しい市場、それだけでなく海外市場の動向によって国内回帰が行われている中で、そこでいかに強い技術力、品質管理等を高めた中小企業がサプライヤーとして仕事を取れるかどうか、それに対して取組をしっかり支援していきたい。
委員長:それでは「技術力の向上に向けた支援」について、委員から温かい意見もあるが、本委員会としては、主管課、企画課による評価と同様にB評価とする。意見としては、着実に成果を上げながら取り組んできており、さらにより高みを目指して取り組んでいただきたいということでまとめさせていただく。
「ものづくりのまち綾瀬」のブランド化促進:委員評価 B
委員:学校との連携に関して、工場見学のほか、工場から学校に来て科学実験教室、ものづくり教室、お祭りなど協力いただいた。副読本には綾瀬の工場で働く人たちや工場の種類などがとても丁寧に子どもに分かりやすいように書かれている。子どもたちが工業に関心を持ち、将来的に綾瀬のものづくりが進んでいけばいいと思う。
委員:ブランド化のPRはどのように行っているのか。
工業振興企業誘致課:市役所の1階ロビーでものづくり研究会の製品を展示し、カタログも配架し、市民が製品を買えるようにしている。あやせ工場スマートナビというホームページにも製品PRを掲載している。産業まつりでは実際に製品を手に取れるようにし、製作背景なども紹介している。2年前は製品で肉を焼く実演も行った。そういった場面で市民に知ってもらう機会を創出している。
委員長:なぜ綾瀬市にものづくり企業が集積しているのか。自動車の関係が大きく影響しているのか。
工業振興企業誘致課:昭和40年代に、京浜工業地帯の公害を契機に神奈川県がいわゆる工業団地を作っていったところからスタートしている。綾瀬工業団地、さがみ野工業団地、早川工業団地もそうした形で施工されて、いわゆる企業集積、移転も含めて行われてきた背景がある。また、県北側と県南側に自動車生産工場があり自動車部品産業がもともと集積していたことから、そこに関わるサプライヤーとして工業団地で来るところと、あとは自然発生的に発生した工業会という形で吉岡と綾北地域に集まってきたという背景がある。
委員長:ブランド化の際に、企業集積の歴史を分かりやすく紹介することはとても大切。産業観光やものづくりのブランディングの際に、歴史と合わせて紹介すると非常に関心も出ると思う。
工業振興企業誘致課:綾瀬の企業集積のルーツは、綾瀬の工業について紹介する際に必ずふれている。先ほど、教育の関係でも話があったが、総合学習の一環で、綾瀬のものづくりについて教えてほしいと学校から依頼がある。その際も、必ず企業集積のルーツについて子どもたちに説明している。ルーツが大切ということは認識した上で事業展開している。
委員長:それでは、「ものづくりのまち綾瀬のブランド化促進」については、本委員会の評価としてはBとする。コメントも先ほどと同様、着実に取組の成果を挙げているが、所管課の課題認識にあるように、さらなる仕掛けが必要であり、こうした課題の解消に向け、さらに取り組んでいただきたいという意見とする。
担い手づくりへの支援:委員評価 B
委員:夏休みのみのアルバイトも報酬はちゃんと支払われるのか。誰でもできるのか。
委員:アルバイトについて、今年は高校生の応募があった。高校生のアルバイトは事例が少ないので、まずは学校の許可と保護者の許可を確認する。そういうステップを踏んで一つの形を作っていけると、夏休みにアルバイトをして将来就職するという道も開けていくのではないか。いま少し動き出しているところだ。綾瀬市には工業高校がない。私の夢は、綾瀬の工場の現場に授業の一環として参加できるような仕組みをつくること。例えば、大学生の授業単位認定のように、高校生が1週間、1コマ2コマ、綾瀬市に来て工場の技術を経験できる。それが就職への道につながるなど、そのような取組も将来始まるのではないかという予想をしている。それをぜひ綾瀬市で実施できないか。可能なら綾瀬高校で工業科などができるといい。他の高校からでも、ものづくりに進みたい生徒はその授業のみ選択履修できて、その受け皿を綾瀬市にするなど、市と学校と企業がつながることができないだろうかと思っている。
委員:近隣にある専門学校や高等専修学校などは工業とは関わりがないのか。
委員:今年は6人採用したが、全員工業科出身ではない。小学校で工場見学に行った子どもが高校生になったとき、そういう授業を選択できるように仕組みが変わったら、またものづくりに入ってくる人が増えてくると思う。
工業振興企業誘致課:委員の思いは私たちと同じだ。市内の全ての私立・公立の高校とはつながりがある。ただ、事業化には教育委員会という大きなハードルがある。自由度が高いのは大学のほうである。今年から横浜にある大学とコラボレーションして、新しくできた学部の学生が授業単位を取れる範囲で綾瀬市内の企業に来て、いろいろなことを分析してみようというプロジェクトを発信している。そういったケースを少しずつ増やし、大学の在学中に綾瀬市の企業のおもしろさを知ってもらい、その後、ものづくりを希望する人がまた綾瀬に来てくれないか、私たちとしてはそうしたビジョンを持ちながら大学と連携していく。いわゆる事業の一環として市内企業に来てもらうということを今年から実施していく。
委員:先ほどプロジェクト概要資料に、ベトナムの方を担い手に、という話があった。それについて教えていただきたい。
工業振興企業誘致課:アイデムという人材派遣会社のグローバルネットワークチームは、ベトナムで1番2番の教育レベルを誇るハノイ工科大学と人材派遣の事業を展開している。神奈川県はベトナムとの関係を強化しており、今回アイデムと連携をした。インターンシップという形で県内企業に来て、学習や経験を積み、将来はその会社に基本的には入社していただく、学生も入りたいと思って来日するので、そういったスキームの中で今回初めて県が取り組み、そのステージが綾瀬市となる。当課で調整役を担当しており、ちょうど昨日、綾瀬市に学生が来た。現場を見たが、彼は非常に熱心で、実際の日本の機械、品質、生産現場、そうした部分からの刺激をとても感じているようだ。工科大学の学生なので、来日する際は「技術・人文・国際」というエンジニア等に近い在留資格で来る。日本の在留資格上は、現場作業のものづくりにはなかなか携わりにくい。ただ、会社の設計やマネジメント等、中枢の部分、いわゆる幹部候補生的な役割を担える人材になると思うので、そうした外国人材を引き入れて会社を強くしていくという運びで考えている。もう1点、技能実習生についても、綾瀬市と綾瀬市商工会で連携して積極的に受け入れているが、それは現場の生産活動を維持するために必要な人材だ。今回のハノイ工科大学との連携は、もう少し中枢の層に必要な人材ということで、そこはしっかり補填していこうという形でプロジェクトを組んでいる。
委員:そうした方々は技術を習得して永住する人と帰国する人、どちらが多いか。
工業振興企業誘致課:どちらを選ぶかは個人によるところだ。永住権を持たない方も、永住権を持っている方もいる。例えば、今回のハノイ工科大学から来ている人は、仮に採用になった場合には5年、10年、できるだけ長く自分が学んだスキルを生かしながら日本の高い技術力を習得していきたいと話している。ベトナムには故郷の家族を大事にする文化があるので、いずれ帰国することもあるだろう。日本で学んだことをベトナムで生かして起業したいという夢を持つ人たちもいれば、永住権を持って綾瀬に住み、いわゆる帰化する人たちもいる。
委員長:所管課の一次評価の課題への対応に関して、スキルアップやモチベーションを高める仕組みを構築するとある。技術開発や技術力の向上など、その辺りはしっかり取り組んでいるのだろうと思うが、昨今の様々な組織の中の人間関係のあり方、コミュニケーションやマネジメントの関係で、横の連携や研修の必要性については、綾瀬の場合は特にはないか。
工業振興企業誘致課:ここで記載していることは、合同研修に参加した一番古い社員が長年勤めて役職が上がり、管理者に昇格してきているため、企業の垣根を越えた合同研修の参加者という横軸として、同期だった人とまた合同の管理職研修等を通じて意識を共有してもらうという枠組みを作っていこうと思っている。しかし、個別の会社のマネジメント体制や社員の管理体制等はまだリサーチしていないのが現状だ。
委員:人手不足の対策について良い知恵はないか。
委員:一番簡単なことは、実際に工場を見ること。例えば、私の工場の従業員は120人いるが、18歳から85歳まで働いており、男性が60人、女性が60人。外国人が60人、日本人が60人。委員が探している答えは全部私の会社にあると思う。皆が採用したくない人も採用したい人も一緒で、競争になる。私の会社では働きたい人は全部、障がい者も含めて採用する。先生が生徒を紹介するとき、おかしいことだが、多くの場合、続かないからやめたほうがいいと言う。しかし、本人とよく話をして1日3時間からスタートし、少しずつ時間を延ばし、結果、週5日8時間で働けるようになる。だから、人手不足の会社は採用しない理由が多いのだと思う。そういうところを全体でどう考えるか、いろいろな問題が本当は解決するのではないかと思う。そういう会社作りをすると、働ける人はもっといるはず。そうした掘り起こしみたいなことをするといいのではないかと思う。補助金制度にも、本人が希望していても有期雇用契約の場合は対象外になるなど、疑問な点もある。いろいろな課題を解決しながら取り組んでいる。
委員:今まで綾瀬市としては工業団地を計画的に誘致してきた。中小企業には大企業にはない柔軟性があり、それが強みで、それを生かしていかなければいけない。
委員長: 3つ目の「担い手づくりへの支援」について、主管課、企画課ともにBということもあり、当委員会としても評価をBとする。現状認識、課題認識について、企画課が主管課による課題認識をまとめているので、これをベースにし、ただ、各委員の意見交換にあった高等教育機関との連携をさらに取り組んでいくということと、市内の優良事業所の取組を顕彰し、周知していくような工夫をすることを望むというような表現でいかがか。
委員:工場見学等で現場を見れば、実際に働いている人が見えてくる。研修として現場の視察も大いにやるべきだと思う。
委員長:オープンファクトリーを実際に拝見したことがある。綾瀬の場合は、本当に中小企業の社長や所長の方々、中で働いている方々、女性も含めて皆さんが笑顔で一生懸命にやっていた。あのような一体感は、綾瀬市の工場団地で行われるオープンファクトリーのすばらしい魅力であり、大いに誇るべきところだ。市内及び周辺はもちろん、さらに対外的にPRするとよい。それがこの担い手づくりへの支援にもつながっていくと思う。
育てる2 外国人市民が活躍する多文化共生のまちづくりプロジェクト
(主管課より資料に基づきプロジェクト概要及び一次評価結果を説明。企画課より二次評価結果を説明)
外国人市民への行政サービスの充実:委員評価 B
委員:通訳サービスについて、他の市町村にもあると思うが、他とは違うサービスがあるのか。
市民活動推進課:綾瀬市の通訳サービスは、電話またはテレビ電話で、通訳側・行政側・市民側の3者通訳ができる。開庁時間なら窓口でも電話の問い合わせでも、3者通訳ができるようになった。
委員:保険証の申請や病院での通訳など、医療関係はどのような支援があるか。
市民活動推進課:神奈川県とMICかながわが共同で、県内の協定医療機関から派遣依頼を受けて医療通訳ができるようなシステムを運用している。
委員長:通訳サービスの整備により担当課職員のみで対応できるケースが増えたけれども、課題として外国人市民対応力に差が生じているとあるが、なぜか。
市民活動推進課:通訳サービスは全庁的に利用できる状況だが、職員の習熟度に関して課題が残っている。企画課の評価にもあったが、それは引き続き全庁的に取り組むことで、徐々に習熟度をあげて解決できると思っている。
委員:綾瀬市全体で日本語教室が8教室は妥当なのか。
市民活動推進課:ニーズからすれば充足している状況。8か所は市内に点在しているので、近い教室を案内している。計画策定時より教室は増えているが、状況を見てニーズができた段階で、新たな団体立ち上げの協力等にすぐ対応していきたい。
委員:ベトナムやスリランカ、ラオスなどは、工場誘致の関係で増えているのか。
市民活動推進課:ベトナムに関しては、もともと大和市に難民センターがあり、その経過から近隣の綾瀬市にも多く住んでいる。また、市内の工場で働く技能実習生も住んでいる。
委員長:これは当委員会としては、B評価とする。行政サービスの体制の拡充ということでは、常時対応可能な通訳サービスの整備により、着実に進められてきているが、まだ全庁的な実践的な対応については課題がある。そういうことでよろしいか。
多文化共生の促進:委員評価 B
委員:ステップ2にある日本語学習支援について、教育委員会でも、外国人の子どもたちの言語については大きな課題がある。今は児童生徒7500人のうち約370人が外国につながりのある子どもだ。中学校1校と小学校7校に国際教室を設置しているが、国際教室に通っている間は学ぶことができても、普通の教室に戻ったときのフォローや日常生活について課題がある。「にぬふぁぶし」という市民団体に協力してもらい、日本に来たばかりの子どものフォローをしている状況だ。子どもが小学校低学年のうちは言葉が通じなくてもコミュニケーションしていけるが、中学年以降になると難しい。家庭でも母親は日本語を話せないこともある。ぜひ、大人を対象にした日本語学習支援も、重点的に行っていただきたい。工場の一部では支援教室も開いており、そうした取組もすばらしいと感じる。
市民活動推進課:昨年、夏休みも日本語学習をできるよう、北の台小学校で「にぬふぁぶし」が講座を開いた。こうした事例を少しずつ増やしていきたいと団体も考えており、日本語教室のプレスクールなど、さまざまな場面で協力していきたい。また、子どもが学校で少しずつ日本語を話せるようになっても、家で母国語だけで話していると、話す機会がなく、すぐ忘れてしまうという環境があると認識している。スリランカはムスリムの女性が多く、ムスリム女性の教室が1つできている。そちらと協力した多文化親子交流事業は、日本人と繋がりをつくり、少しでも日本語を話す環境に一歩出向いていただくようなきっかけになればという思いで実施している。こうした事業をさらに増やしていきたいと考えている。
委員:自治会ではごみの問題がある。そうした日本語教室を開いて、どの程度の割合で参加しているのか。また、会社ではどのような教育をしているのか。会社でもごみの分別はあるから、おおよそ分かるようになると思う。その辺りを教えれば外国人の方への貢献度が非常に高いと思う。
市民活動推進課:来日する人には、全く日本語を話せない人も、ビジネス目的で来て日本語を話せる人もいる。何か困りごとがある際には日本語を話せる人を介して対応できることもあるが、日本語が分からない方はいずれ自分自身が生活で困ってしまうので、同郷の人から勉強の必要性を伝えてもらえたら幸いかなとは思う。しかし、私たちは行政であるので、公平に機会をつくることは必要だ。それから、スマートフォンのアプリケーションの活用も大切。外国人市民も、自動翻訳を利用して市のホームページを閲覧している。全く日本のことがわからないということは実はあまりないのではないかと思っている。今は市の職員がもつ公用スマホにも翻訳アプリを入れている。ちょっとした工夫で会話ができるようになる。そういった部分を整備し、また、地域の方にもPRして広げているところだ。そういったものを駆使すれば、日本語を話す話さないに関わらず、コミュニケーションとして意思疎通を取れるような環境が生活の中でもできると思っている。そうしたことを発信しながら、工夫しながらコミュニケーションを取っていくことができるといいと思っている。
委員:来日する方は若い人が多いからスマホは得意だ。そういう取組を進めていけば十分に足りるのではないかと思う。良い取組だからさらに進めていただきたい。
委員:ステップ2の課題への対応について、多文化共生に関心の薄い層の集客を図るということがある。それはどのように多文化共生の必要性や大事さを伝えていくのか。今までどのようにしてきたのか。また、多文化共生とは、どのような姿が理想なのか。綾瀬市内でどういう状態になれば達成された状態となるのか。
市民活動推進課:行政が開く講演会に来る人はテーマに興味がある人なので、無関心層に対するアプローチにならない。イベントなど気軽にすぐ行けるようなきっかけづくりがとても大事だと思う。そうした取組の中では、昨年に開催されたズンバ教室、キッズフェスティバル、今年のハッジバザー。去年のキッズフェスティバルは宗教的な理由で男性は参加できなかった。今回のハッジバザーはその部分は取り除いて男性も来場できるイベントに変えて開催し、ある程度成功したと思っている。イベントで異国文化に触れて理解を深められることも増えていくと思うので、小さいイベントをコンスタントに提供していく方が自然と共生感覚が結びついてくると思う。また、理想像については、総合計画の最初のページにイラストつきで載せている。地域で外国人も日本人も垣根なく、地域の一員として肩を組んで楽しむ、困ったときには助け合う、そういう垣根のない状況ができることが一番。活躍する外国人というのはやはり一生懸命働いて税金も納めて、みんなの礎になってもらうというのも含めて、そうした日本の社会の中に普通に溶け込んでいるということがおそらく理想なのではないかと思う。
委員:宗教について聞きたい。例えば、学校での生徒と保護者の対応や、職場で仕事を休憩して礼拝するなども道徳の一つとして教えているのか。私たちは全くそういう習慣がない。会社や市役所が何かアドバイスしているのか。
市民活動推進課:市から教育現場には直接具体的な対応の指示はしていない。学校でなにか問題があったとは聞いていないので、宗教の違いに対する理解については先生がよく伝えているのではないか。学校でうまく対応できていると認識している。
委員:私の会社では、宗教上の問題は最初に日本人に対して説明する。それから、採用する前に本人に確認する。6割から7割の人は、お祈りはしなくても大丈夫だと言う。働きたいからそう言う、というのが実情だと思う。
委員:学校によっては、お祈りの時間がある子どもがいるようだ。礼拝の部屋がないので校長室の一部を借りて、お祈りの時間を設けているという話も聞いたことがある。クラスの子どもには担任からきちんと説明していると思う。
委員:事故や犯罪等はどのように行政は対応しているのか。これは警察関係だろうか。
市民活動推進課:犯罪は警察が直接対応するため、行政が間に入ることはない。
委員長:多文化共生の促進について、当委員会の評価としては、ステップ1から3まで通して、評価はBで妥当ではないか。ステップ1の外国人市民への日本語・日本社会の理解促進を図る、地域への共生意識の啓発を図るということでいうと、この行政としての取り組みは着実に生きてきている。また交流の場も創出されてきている。今後は、引き続き多文化交流の主催団体の活動について、自立かつ自主的な活動に向けて支援することが課題だろうということでまとめさせていただく。
外国人市民等の活躍の支援:委員評価 A
委員:昨年、市役所中庭で開催されたスリランカのフェスティバルに行った。子どもは綺麗なスリランカの衣装を着て、一緒に写真撮影するなどの交流ができた。普通は外国籍の子どもにいきなり話し掛けることはないと思うので、交流の場は貴重な機会である。スリランカのカレーづくり講座も参加したが、直接教わることができ、とてもいい研究になった。スリランカの母親たちと話すことがなかったので、とてもいい経験だ。ぜひまた広めて続けていただきたい。
委員長:それではステップ1から3の進捗状況について、当委員会としてはA評価でよいか。今後の課題として、主管課、企画課で挙げているが、交流イベントにおいてさらに積極的な外国人市民の方の関わりができるよう、いろいろな形の働きかけが大切ではないかと思う。自分たちがどこまで関わり、加わっていいか分からないというような部分もあるのだろうと思う。その辺りの壁をもっと行政の方から破っていくという取組が必要だと思う。
この記事に関するお問い合わせ先
綾瀬市役所 経営企画部 企画課 政策経営担当
電話番号:0467-70-5635
ファクス番号:0467-70-5701
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


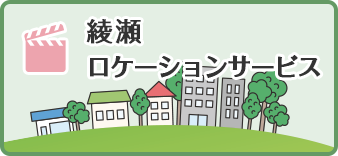
更新日:2024年10月25日