ナラ枯れの被害拡大について
市内で「ナラ枯れ」の被害が発生しています。
平成29年度に神奈川県内で初めてナラ枯れ被害が確認されて以降、被害区域が拡大し、市内でもナラ枯れが確認されています。
ナラ枯れとは

ナラ枯れの木に見られるフラス
「ナラ枯れ」とは、体長5ミリメートル程のカシノナガキクイムシ(通称:カシナガ)が媒介する「ナラ菌」によって、健全なコナラやミズナラ等のナラ類やシイ・カシ類の樹木が、7月から9月ごろに集団的に枯れるものです。
ナラ菌は、カシナガが樹木の幹に穴を開けて内部に入り産卵する際に持ち込まれ、ナラ菌が樹体内に広がり通水が阻害されることによって、樹木が衰弱し起こります。一般的には太い木や高齢の木ほど侵入されやすく、枯死しやすいといわれていますが、カシナガが侵入してもその全ての樹木が枯れるわけではありません。
ナラ枯は紅葉には早い時期に山の木々が茶褐色に変色していること、カシナガが侵入した樹木の根元を見るとフラスと呼ばれる木くずが積もっていることなどから見分けられます。
大きな木の根元に木くずが積もっている写真 拡大画像 (JPEG: 16.9KB)
被害対策
主な被害対策・拡大防止策は、薬剤による伐倒くん蒸や予防材の注入、粘着シートによる被覆処理があります。
なお、ナラ枯れの被害木の処理は各樹木の所有者が行う必要があります。被害木の処理方法が分からない際には専門業者にご相談ください。また、専門業者がわからない場合にはみどり公園課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


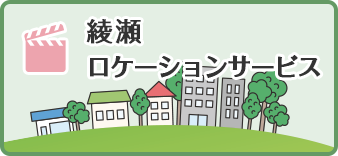
更新日:2024年04月19日