令和5年度第2回綾瀬市青少年問題協議会会議録(令和6年2月22日開催)
審議会等の名称
令和5年度第2回綾瀬市青少年問題協議会
開催日時
令和6年2月22日(木曜日) 13:00~14:55
開催場所
綾瀬市役所事務棟6階 視聴覚室
第1回綾瀬市青少年問題協議会 議題
議題
- こども大綱について
- 綾瀬市いじめ防止等対策委員会との連携について
報告
-
綾瀬市いじめ問題再調査会について
-
綾瀬市青少年相談室の活動概要について
出席者
- (委員)
- (会長)古塩政由
- (副会長)榎本源𠮷
- 畑井陽子
- 小川富久子
- 星野敏雄
- 原和子
- 栗原芳子
- 澁谷敏夫
- 古塩佳子
- 久本義一
- (事務局)
- 健康こども部長
- こども未来課長
- 教育指導課長
- 他事務局員2名
傍聴者数
0名
内容
1 開会
2 会長あいさつ
3 諸般報告
(事務局)
〇定数について、13名中10名の委員が出席で定足数に達した旨を確認
〇会議傍聴者がいない旨を確認
〇会議記録について要点筆記とする旨を確認
4 議題
(1) こども大綱について
(事務局)
〇資料に基づき、こども大綱について説明
〇説明完了後に、質疑応答と各委員内における意見交換
【質疑】
(会長)
国が定めた「こども大綱」には真新しい事はなく、市町村でこれまで取り組んでいる事柄等が記載されている。国は高い目標値を掲げているが「自国の将来は明るい」と思うこども若者の割合だけ、目標としている値が55%と極端に低い。こども達にとって自国の将来は一番重要ではないかと疑問である。こども家庭庁については、発足時から名称等について「家庭」を名称に加える加えないなど、二転三転の議論がされ、こどもを教育するには「家庭」が一番重要であることから「こども家庭庁」となったようである。
(委員)
集団内で特定の子が強く主張しすぎると、その子が仲間外れにされ、いじめに繋がってしまう。その時に、我々大人が、どうやって接するかが大事である。こどもにとって家庭は重要だが、今は家庭内でも殺人事件などの問題が発生している現状である。
(委員)
自分が育児をした時は、こどもと向き合って重圧がかかって育児をしたので、育児は辛い印象であったが、こどもは自分が育てるのではなく、社会が育てるのだと、育児についての発想を変えた事により重圧がなくなった。日本が社会全体で育児をしていく、大人みんなで子育てしていく社会になるよう意識を変えていければよいと思っている。そうすることで、最近の痛々しい事件等が減るのではないかと思っている。こども大綱については、いまさら「こどもまんなか社会」なのかと言いたい。いつでも社会の真ん中はこどもだと思っている。全ての人が自分も子育てをしている社会の一員であり、社会が子育てを背負っていく位の気持ちになってもらう事が大事である。
(会長)
国は、家庭から養育機能がなくなって、さらに地域から養育体制がなくなってきていると感じてきているので、家庭崩壊や地域崩壊の危機感から、再度の「こどもまんなか社会」を掲げて、こどもを社会の真ん中に据えて施策を進めていくようである。これからは、昔のように社会でこどもを育てようとの事だが、「自分には自分らしさというものがある」と思うこども・若者を90%にする、ほとんどの人が自分らしさを持っている状態を目標にしている。
(委員)
自分らしさだと、何をやってもよいとなってしまう。
(委員)
こども大綱54ページ「こどもまんなか社会に向かっている」が現状15%しかないので、こどもまんなか社会は理想であるが、社会の人はそう思っていないのが現実であることを理解した。こどもの権利条約が社会にも浸透しておらず、綾瀬市も権利条例がなく、日本中でも条例があるところは少ない。施策に押し込むことによって、こどもの権利について意識を持っていない大人の意識を変えていかなければと思っている。こどもを自分の所有物と思ってしまう親も多く、そのことから抜け出せないから育児放棄や育児怠慢と言われるネグレストや児童虐待が起こってしまうのではないかと思い、この大綱が大人に対する警告ではないかと考えている。これからもあらゆる場面で施策にコミュニティスクール等の意見を取り入れてほしい。
(会長)
施策形成の時には、児童虐待など社会の悪いところを是正させる所から始まり、この機会に「こどもまんなか社会」をもう一回見直そうという機会になっている。神奈川県もこども政策に力を入れているが、この目標達成は誰がやるのか。
(委員)
「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と思う人が27%と低い値になっている。出産手当や医療費支援、こども手当や待機児童対策等いろいろ市がやっているのに値が低く認知されていないのは残念だと思う。自分達の世代は支援をしてもらう事ができて嬉しいが、親としては、もらえて当然・やってもらえて当然だと思われている。行政がPRを工夫すれば、もう少し数値は上がるのではないかと思っている。
(会長)
国は、何をみているのかと思う。行政は当然取り組んでいる。全国の市町村はすでに実施している、やっていない市町村はないと思われる。支援の対象とならない方に、支援制度が知られていないだけなのではないか。
(委員)
自分でやるのが当たり前の世代に自分は子育てをしてきたが、「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者が現在97%いて、こども・若者に対する支援が浸透していると思う。助けてくれる人、相談することできる場所があるのはいいことだと思う。
(会長)
頼れる人がいれば自殺率が少なくなるし、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える保護司と話した人の方が、再犯率が減ってきている傾向があると聞いている。
(委員)
自分は問題もなく元気な子と関わることが多いが、こども達の悩み・親にも話せない悩みをどこに出して聞いてもらっているかが心配である。命を絶つしかない状態まで追い込まれたこどもをつくってはいけない。こども一人ひとりを見守っていける社会や大人にならなければいけないと思う。自分は学校関係にも関わっていて、通学時の見守り時に、ときどき心配な子がいる事がある。
(会長)
各学校には、臨床心理に関する専門知識を活かして児童や生徒に相談・支援を行うスクールカウンセラーがいて、心配はないと思っている。
(事務局)
学校現場にはスクールカウンセラーや問題を抱える児童・生徒に関係機関と連携や調整を行ったりするスクールソーシャルワーカーを配置しているので、相談の機会は以前に比べて増えている。こどもが相談場所に行けるかどうかが重要であり、いつでも相談ができるような環境は整ってきている。
(会長)
昔より親との接触頻度が少なくなってきているように思える。
(副会長)
今は親に聞くよりインターネットで調べる方が早い。
(委員)
親とのコミュニケーションが取れていない家庭もあるので、家庭内での話しやすさや空気が大事であると思っている。
(委員)
あなたのいばしょチャット相談といって24時間365日、チャット相談している機関がある。日本人だけではなく海外の相談員も使って相談に対応していて、素晴らしい取り組みである。こどもの声はとても重要で、こどもからのSОSについて意識を高めていきたい。相談窓口も広がってきていると思う。
(会長)
行政や学校での相談体制は整って充実してきているが、相談事案は大きく重くなってきていると感じる。
(委員)
まわりの意識も変わってきている。
(委員)
児童虐待も右肩上がりで増えてきている。どこからの通告かというと、近年は本人からの通報も増えている。増えている要因としては、LINEなどのSNSのツールが増えて使いやすく、ハードルも下がってきているからではないかと思っている。先生からの通告もあり、こどもの変化は先生が気付いている。
(会長)
児童相談所等の相談体制は充実して、相談も件数が増えていて、相談にかかれば解決に向かっていくが、発生する問題を起こさないようにしなくてはならない。
(委員)
都市部と田舎地域では大きく変わってくる。都市部の方が相談は増えてきている。血縁もない地域での子育てに対して、閉鎖的になりケアが行き届いていないと思われる。
(会長)
相談の処理は増えているが、その相談のもととなる問題を発生させないようにしなくては、社会としては解決しないと思われる。
(委員)
先日4歳の子が殺害されたが、保育園幼稚園や学校からの通報が大事だと思う。
(委員)
児童相談所は通告があった場合には、関係機関と連携して対応している。
(会長)
幼稚園にも保育園にも行っていない「未就園児」が問題である。
(委員)
未就園児はたくさんいる。しかし、中には「幼稚園にも保育園に行かせない」未就園主義の親もいる。
(委員)
幼児の徘徊のニュースもあったが、地域の人が声をかけたり相談に乗ってあげたりして、社会となんとか繋がってもらいたい。
(会長)
そのように社会に繋がっていない人をなんとかしなければならないと思う。
(委員)
こどもは変われるので、こどもと関われる時間を確保するのが重要である。そのあたりは大人の問題であるように思う。
(委員)
こども関係のたくさんの支援があるが、その制度など様々な所から見えてくるものがあるのではないかと思っている。
(委員)
こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画のサポートプランを生まれた時から作成して支援すると決めた。そのために子育て世帯を包括的に支援する「こども家庭センター」を全国の市区町村に設置するよう進めている。
(委員)
綾瀬市保健福祉プラザは、しっかりしている。外国籍の家庭やリスクがある家庭のケアも十分に行っている。
(会長)
綾瀬市の外国籍の方は、ベトナムやスリランカ国籍の方が多い。こどもは日本語をすぐに覚えることができるが、学校に入る前に日本的な教育が必要である。
(委員)
先日、ヤングケアラーの保護者の方と話す機会があり、支援については「押し付けるのではなく、何かあった時につかまれる所が多いと嬉しい」と語っていた。
(会長)
ヤングケアラーは支援を受ける方法を知らないのではないか。支援先に繋がる方法を伝えることが重要である。
(委員)
市内で子ども食堂を開催しているが、こどもと大人がどれくらい接しているかが重要で、そのことでコミュニティが広がると感じている。自己主張できる子とできない子を見極める大人の力が最も重要である。
(委員)
両親を殺害した高校生や出産した赤ちゃんを寺に埋めた事件など、こどもの人権について社会全体で考えていかなければいけないし、命に対して大切にするのが重要と思う。結婚妊娠に対してこれからが心配であり、目標の70%に近づけていきたいと思う。
(委員)
大人が注意していても、こどもは大人の目を盗むので細心の注意が必要である。
(会長)
目標への達成手段が明記されていないが、目標値に向けて頑張っていきたい。
(委員)
こどもまんなか社会に向けての相談方法を広報などで周知をしていきたい。大人や 地域で、こどもをみることが根本的に大事なのではないか。
(2)綾瀬市いじめ防止等対策委員会との連携について
(事務局)
〇資料に基づき、綾瀬市いじめ防止等対策委員会との連携について説明
〇説明完了後に、質疑応答と各委員内における意見交換
【質疑】
(委員)
ピンクシャツデーの取り組みについて教えてほしい。
(事務局)
2月28日、最終水曜日にピンク色のシャツや小物を身につけることで「いじめ反対」の意思表示を行うアクションで、教育委員会から各学校にチラシを配布している。綾瀬市立春日台中学校をはじめとして市内の中学校で積極的に関わっていて、今年から小学校に伝えていく取り組みを始めており、小学校でも開催する動きがある。
(委員)
積極的にいじめの認知を行うのは誰が行うのか。
(事務局)
主語は教員である。解決のために、いじめ傍観者も含めて、いかに良い環境をつくるかが大事であると認識している。
(委員)
こども達の感性は無限であり、大人が、いかに良い環境を用意してあげることが重要である。
(会長)
不登校等の問題は、綾瀬市だけではなく全国的な事案であるが、むりやり学校で学ばせることではなく、こども達には、学びの場をたくさん用意して、その人に一番よい所で学ばせるのが重要であるのではないかと思う。
5 報告
(1) 綾瀬市いじめ問題再調査会について
(事務局)
〇資料に基づき、綾瀬市青少年相談室の活動概要について活動状況を報告
〇説明完了後に、質疑応答と各委員内における意見交換
【質疑】
(会長)
いじめ防止等対策委員会と同じような委員であるが、その都度設置するのか。
(事務局)
いじめによる重大事案が発生した場合に、委員は利害関係のない市外の方で、その都度設置する。
(会長)
市長部局で再調査をする意味はどういったものか。専門家が調査するのであれば、結果は同じになるのではないか。
(事務局)
教育委員会部局で解決できれば、そこで終了となる訳であるが、教育委員会部局で 調査したものを、違う組織と違う委員の市長部局で調査することに意味がある。専門家については、国で定められており、医師、弁護士、学識経験者、こどもの心身の発達及び心理に関し知識経験者は必須になる。
(会長)
綾瀬市いじめ防止等対策委員会とは別の会議でよいか。
(事務局)
全く別のものであり、幸い綾瀬市ではまだ再調査会が開催される事案はない。
(2) 綾瀬市青少年相談室の活動概要について
(事務局)
〇資料に基づき、相談受理及び街頭補導の状況を報告
〇質疑等なし
6 その他
(1) 次回会議日程(案)について
(事務局)
〇資料に基づき、今後の会議日程を説明
令和6年10月9日(水曜日)午前10時から綾瀬市役所6階視聴覚室
〇質疑等なし
7 閉会
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


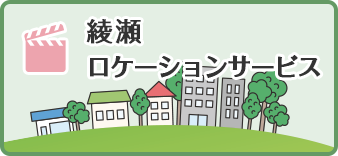
更新日:2024年03月18日