水質用語の説明
以下の用語の説明は、国土交通省関東地方整備局京浜工事事務所発行編集の水質用語集(平成14年3月 改訂版第3刷)から引用しています。
pH(水素イオン濃度)
pHは、水の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標で、水素イオン濃度の逆数の常用対数となります。pHが7の時中性でそれより大きいときはアルカリ性、小さいときは酸性になります。
河川水では通常7付近ですが、海水の混入、温泉水の混入、流域の地質(石灰岩地帯など)、人為汚染(工場排水など)、植物プランクトンの光合成(特に夏期)などにより酸性あるいはアルカリ性になることがあります。
河川でのpHの環境基準値は類型別に定められており、「6.5(あるいは6.0)から8.5」となっています。
BOD(生物化学的酸素要求量)
BODはBiochemical Oxygen Demandの略称です。溶存酸素(DO)が十分ある中で、水中の有機物が好気性微生物により分解されるときに消費される酸素の量のことをいい、普通20℃(度)で5日間暗所で培養したときの消費量を指します。
有機物汚染のおおよその指標になりますが、微生物によって分解されにくい有機物や、毒物による汚染の場合は測定できません。逆にアンモニアや亜硝酸が含まれている場合は微生物によって酸化されるので、測定値が高くなる場合があります。
BODが高いとDOが欠乏しやすくなり、BODが10mg/L(1リットルあたり10ミリグラム)以上になると悪臭の発生などが起こりやすくなります。
河川でのBODの環境基準値は類型別に定められており、「1mg/L(1リットルあたり1ミリグラム)以下」から「10mg/L(1リットルあたり10ミリグラム)以下」となっています。
SS(浮遊物質量)
浮遊物質はSuspended Solidsの略称です。水中に浮遊又は懸濁している直径2mm(ミリメートル)以下の粒子状物質のことで、粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死骸、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿物が含まれます。浮遊物質が多いと透明度などの外観が悪くなるほか、魚類のえらがつまって死んだり、光の透過が妨げられて水中の植物の光合成に影響することがあります。
河川でのSSの環境基準値は類型別に定められており、「25mg/L(1リットルあたり25ミリグラム)以下」から「100mg/L(1リットルあたり100ミリグラム)以下」となっています。
DO(溶存酸素)
DOはDissolved Oxygenの略称で、水中に溶けている酸素の量です。
酸素の溶解度は水温、塩分、気圧等に影響され、水温が高くなると小さくなります。DOは河川や海域の自浄作用、魚類などの水生生物の生活には不可欠なものです。一般に魚介類が生存するためには3mg/L(1リットルあたり3ミリグラム)以上、好気性微生物が活発に活動するためには2mg/L(1リットルあたり2ミリグラム)以上が必要で、それ以下では嫌気性分解が起こり、悪臭物質が発生します。
河川でのDOの環境基準値は類型別に定められており、「2mg/L(1リットルあたり2ミリグラム)以上」から「7.5mg/L(1リットルあたり7.5ミリグラム)以上」となっています。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


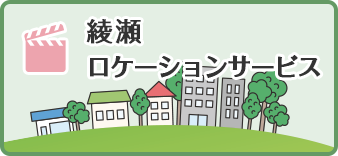
更新日:2024年08月19日