児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進することを目的としています。
対象者
次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(障がい児の場合には20歳未満))を監護している父若しくは母、又は父若しくは母に代わって児童を養育している方(里親は除く)が対象です。
支給要件
下記の要件にあてはまる方が、手当を受けることができます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が法令に定める程度の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
次のような場合は手当は支給されません
- 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき、少年院等に収容されているとき、里親等に預けられているとき
- 請求者が、婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
(注意)住民票の有無に関わらず、生活を共にしている場合などを含みます(養育者を除く)
手当月額(令和6年4月分から)
手当月額は、児童数および所得額により異なります。
また、毎年の消費者物価指数の変動に応じて改定する物価スライド措置がとられています。
その結果、令和6年度の児童扶養手当月額が3.2%の引き上げとなりました。
| 児童数 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
|---|---|---|
| 1人 | 月額45,500円 | 月額45,490円から10,740円 |
| 2人 | 1人の額に 10,750円を加算した額 |
1人の額に 10,740円から5,380円を加算した額 |
| 3人以上 | 3人目から1人増えるごとに 6,450円を加算 |
3人目から1人増えるごとに 6,440円から3,230円を加算 |
手当額の減額(一部支給停止措置)
児童扶養手当は、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する場合、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。
受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方には「重要なお知らせ」、「一部支給停止適用除外事由届出書」を通知します。
「就業している」などの一部支給停止適用除外事由に該当し、定められた期限までに手続きを行うことで、今までどおりの金額を受け取ることができます。
期限までに必要書類の提出をいただけない場合には、手当額が2分の1に減額されます。
公的年金給付等との併給(平成26年12月から)
受給者又は児童が、国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受給している場合(加算対象となる場合や請求すれば受けられる状態になった場合を含む)は、公的年金等受給額(月額換算後)が児童扶養手当(月額)より低額の場合、その差額を児童扶養手当として支給します(一部支給の場合は、一部支給額からの差額となります)。
障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭の皆さま(令和3年3月分から)
児童扶養手当法の改正に伴い、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害基礎年金など(注釈1)を受給している方の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。なお、障害年金以外の公的年金等を受給している方(注釈2)の改正はありません。
- (注釈1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金
- (注釈2) 遺族年金、老齢年金、労災年金などの障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
変更点(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります。
これまで、障害基礎年金などを受給している方は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
変更点(2)支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
申請方法
- すでに児童扶養手当受給者資格者として認定を受けている人:申請不要
- それ以外の方:こども未来課に申請が必要になります。申請に必要なものはこども未来課までお問い合せください。
所得制限限度額(平成30年8月から)
請求者および扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上にある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
| 扶養親族等の数 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | 配偶者 扶養義務者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
| 5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
- (注意)「前年の所得」とは、必要経費(給与所得控除等)を差し引いた後の額に、前年に受取った養育費の8割相当額を加算した金額です。
- (注意)前年の所得を上の表に適用し、制限額未満の所得であれば手当が全額又は一部支給されます。
- (注意)扶養人数は、所得審査対象年に扶養している人数になります。
- (注意)扶養義務者とは、民法877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
- (注意)所得制限限度額は、法律の改正により変わる場合があります。なお、平成30年8月分(12月支給分)から、所得制限限度額が引上げられました。
下記の諸控除があるときは、その額を所得額から差し引いて制限額表と比べてください。
| 請求者 | 控除額 | 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 障がい者控除 | 27万円 | 障がい者控除 | 27万円 |
| 特別障がい者控除 | 40万円 | 特別障がい者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
| 寡婦控除 (対象児童の母は除く) |
27万円 | 寡婦控除 (対象児童の母は除く) |
27万円 |
| ひとり親控除 (対象児童の母及び父は除く) |
35万円 | ひとり親控除 (対象児童の母及び父は除く) |
35万円 |
| 老人扶養控除 同一生計配偶者(70歳以上の者) |
10万円 | 老人扶養控除 | 6万円 |
- (注意)雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除相当額を控除します。
- (注意)社会・生命保険料相当額として一律に8万円を控除します。
- (注意)同一生計配偶者(70歳以上の者)・老人扶養親族・特定扶養親族がある方は、上記の額を限度額に加算し、扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた人数とします。
- (注意)特定扶養親族がある方は15万円を限度額に加算します。
- (注意)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族は、税制上は特定扶養親族ではありませんが、児童扶養手当においては申立書により特定扶養親族の控除を受けることができます。
- (注意)譲渡所得の特別控除(公共用地の取得に伴い、土地建物を売却した場合等の特別控除)等を受けている場合も控除を受けることができます。
- (注意)個人住民税の基礎控除10万円引き上げに伴い、給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げます。従来の控除額に合わせるため、給与所得・公的年金・雑所得金額に係る所得金額から追加で10万円を控除して手当額を算定します。
支給方法
手当は、認定請求をした日の翌月分から支給され、奇数月(各月とも11日、11日が休日等の場合は、その直前の営業日となります。金融機関によっては数日ほど遅れることがあります。)にそれぞれ前月分までの手当が、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
| 支払月 | 支払対象月 |
|---|---|
| 1月 | 11、12月 |
| 3月 | 1、2月 |
| 5月 | 3、4月 |
| 7月 | 5、6月 |
| 9月 | 7、8月 |
| 11月 | 9、10月 |
申請方法
こども未来課子育て支援担当で申請します。
申請手続きには、次の書類が必要となります。その他必要書類は、個別に異なるため、事前にご相談をいただいてから必要書類を案内します。
必要な書類
- 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)
- 通帳等(手当の振込先が分かるもの。ゆうちょ銀行の場合は、振込用店名、口座番号が確認できるもの)
- その他必要書類
受給中の方が行う手続き
児童扶養手当現況届
現況届とは、受給資格の確認や手当額変更のための更新手続きです。
認定を受けた場合、受給者本人が毎年8月に現況届けをしていただくことになります。
現況届をしていただかないと、11月分以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出のままですと受給資格がなくなりますので注意してください。
各種変更手続き
次のような場合は、速やかに届け出をしてください。
- 住所変更(市内で転居した場合や市外へ転出する場合)
(注意)市民課だけでなく、こども未来課での手続きが必要です - 手当の振込先金融機関の変更
- 受給者及び児童の氏名の変更
- 同居者の変更(同居者が転出した、新たに同居者が増えたなど)
- 監護する児童の状況の変更(監護する児童の増減があったときなど)
- 受給者や児童が、国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
- 児童が、父又は母の受けている国民年金、厚生年金などの公的年金や恩給などの額の加算対象となったとき
(注意)6と7は、請求すれば受けられる状態になったときを含みます。
児童扶養手当は、年金の受給権を取得した年月に遡って計算をするため、その間に支払われた手当や差額等は返還していただきます。
資格喪失手続き
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。このような事由が発生した時は、すぐに届け出てください。
資格がなくなってから手当を受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還していただく事になりますのでご注意ください。
なお、偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、罰せられることがあります。
- 受給者が、結婚したとき
- 受給者が、婚姻の届け出をされなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
(注意)住民票の有無に関わらず、生活を共にしている場合などを含みます - 手当の対象になっている児童を監護しなくなったとき
(注意)児童の婚姻なども含みます - 児童が、児童福祉施設等へ入所したとき、少年院等に収容されたとき、里親に預けられたとき
- 父又は母が遺棄や生死不明で受けている方は、父又は母が見つかったとき、連絡又は仕送りなどがあったとき
- 父又は母が拘禁で受けている方は、拘禁解除になったとき
- 父又は母が障害で受けている方は、その障害が児童扶養手当法で定められている程度より軽くなったとき
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


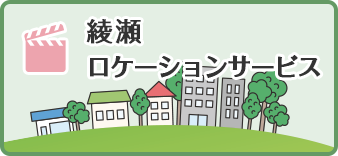
更新日:2024年03月29日