綾瀬きらめき市民活動推進条例逐条解説
綾瀬きらめき市民活動推進条例逐条解説・Q&A
質問: なぜ条例を制定する必要があるのでしょうか。
綾瀬市は、総合計画である「新時代あやせプラン21」の中で市民活動をまちづくりに欠くことのできない重要なパートナーとして位置付け、その自立、自主性を尊重した中、市民・事業者・行政の役割分担を明確にし、お互いがその機能を充分発揮できる環境づくりのための施策を協議するために平成13年7月に綾瀬市市民活動推進検討委員会を設置し、提言書を提出していただいています。提言書では市内の市民活動を行う団体に行った実態調査の結果をふまえ、具体的な10の施策が提言されました。(市民活動推進に関する提言書を御参照ください。)
条例の制定は具体的な施策の一つとして設けられており、市民協働による真に豊かで魅力と活力にあふれる地域社会の実現のために、市民活動を推進する施策の実現に向けての基本的事項の実効性を保証するために制定するものです。
質問: 特定非営利活動促進法(NPO法)がある中で、市が条例を定めるのはなぜでしょうか。
回答: NPO法は、一定の市民活動を行う団体に対し法人格を与え、多数のNPO法人が生まれその活動により公益の増進に寄与することを目的として制定されているものです。
NPO法に基づいて法人格を取得する団体は、将来ともに市民活動団体・グループ全体の10%にも満たないと見られています。
各自治体が市民活動に関わる条例を制定する狙いのひとつは、NPO法による法人格を得られないような小規模な団体の支援あるいは協働を図って地域の公益の増進を図っていこうとすることにあります。
質問: 条例名を「綾瀬きらめき市民活動推進条例」としたのはなぜでしょうか。
回答: 条例名は条例の一部を成すものであり、内容を的確かつ簡潔に表すとともに、市民の心に響き親しまれる名称にしたいとの願いから、市民活動の推進に関する条例検討委員会で提案された6案の中から議論の上事務的ではなく市民の熱意が感じられる名称であるとして決定されました。
なお、条例名の「きらめき」や前文の「きらきら」は市民活動の活性化への期待を示す適切な表現と受け止めています。
質問: 全体的に表現が抽象的ではないでしょうか。
回答: 市民活動は、本来市民の自由な創意と情熱から生まれ展開されるものであるとの考えから、本条例はあくまで基本的な理念をうたうものとしたいと考えたために、そのような印象を持たれたものと思われます。市民活動に関わる環境や、市民の考え方は今後大きく変化していくと推測されることから、具体的な施策等については、条例制定後に設置される市民活動推進委員会において検討していく予定です。
質問: 本条例の制定は、他条例等との整合性など影響が大きく、市の関係各課による十分な調整、協議を行うことが必要と考えますが、将来制定が予想される条例との整合性はどのように図っていくのでしょうか。
回答: 今後制定が予想される条例に、自治基本条例やパブリックコメント条例などが挙げられますが、現在制定の予定はありません。将来制定が予想される条例については、制定時に市民活動推進条例との整合を図ってまいります。
前文
21世紀を迎えた綾瀬市は、緑と文化が薫るふれあいのまち あやせを将来都市像に掲げ、市民一人ひとりがいつまでもこのまちに住み続けたいと思えるまち、一度は住んでみたいと思えるまちをめざしています。
人々の価値観や生活様式、ニーズが著しく個性化・多様化する一方で、社会全体の急速な少子高齢化や高度情報化の進展、経済活動の停滞、国や自治体の財政困難、治安の悪化、大規模災害の危険、さらには地球規模の環境問題や世界平和への不安など、多くの困難な課題が山積していることは否定できません。
こうした課題に対し、新たな発想から勇気を持って自ら取り組もうとするさまざまな市民活動が活発化していることは、明日への大きな希望を抱かせます。大切なことは、そうした志を持った市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いの立場や思いを尊重し、良きパートナーとして力を合わせる、真の市民協働による成果をあげることであり、その中心的な役割を担う市民活動がより一層活発に展開される地域社会を創造することだと確信します。
ここに市民活動がきらきらと光り輝く、新しい時代の綾瀬のまちづくりの推進を誓い、「綾瀬きらめき市民活動推進条例」を制定します。
趣旨
前文では、現在の社会情勢と本市の将来像をふまえた条例制定の経緯を述べ、市民活動の意義や有用性、目指すべき地域社会のあり方を示したものである。
解説
社会情勢の変化には著しいものがあり、急速な少子化・高齢化をはじめとした多くの社会的課題や多様化・複雑化する市民ニーズの全てに行政だけでは対応することができなくなってきている。
一方、地方の時代が提唱され、自分達の住む地域のあり方を自分達で考え、地域の特性を生かした魅力的なまちを、自分達の手で創っていこうとする市民の気運も高まりつつあり、地域コミュニティによる課題の解決のみならず、より広い範囲で社会の抱える課題に直接または間接的に作用する様々な市民活動が生まれてきている。
こうした新しい時代の到来を踏まえ、これからのまちづくりは、市民協働による真に魅力と活力あふれる地域社会の実現が望まれており、市民活動はその一翼を担うものとして、これまでもボランティアをはじめとしたさまざまな公益的な活動により社会を変えてきた経緯もあるが、その置かれている現状は、未だ能力や役割を十分に発揮できる環境が整っていない。
そこで、本条例により市民活動を推進し、真の市民協働による地域社会の実現を目指すべく、「綾瀬きらめき市民活動条例」を制定するものである。
Q&A
質問: なぜ前文をつけたのでしょうか。
回答: 市民活動に関する条例については、各自治体に作成の義務は無く、政策的な観点から制定されるものです。独自の政策の方向性を示すためには、現在の社会情勢と本市の将来像をふまえた条例制定の経緯を述べる必要があるため前文をもって説明しました。
なお、前文をもつ条例はその傾向としてその制定に必然性があるものや制限的な内容のものにはあまり見られずに、理念的・啓発的な色彩を持った条例に付される場合が多くみられます。
質問: 前文だけなぜ口語体なのでしょうか。
回答: 今までの条例の形態を残しつつ、市民に親しみやすくするために条例名に市民活動をイメージした文言を盛り込むともに、前文は口語体で作成しました。
なお、現在県内で6市において市民活動を推進する条例が制定されていますが、これら先駆的事例の中でも3市がこの形態をとっており、条例検討委員会において慎重に検討された結果です。
質問: 条例に今日的課題を記載することについては、社会状況の変化がないことを前提として、今日的状況を恒常的に考えてしまう危険性があるのではないでしょうか。
回答: この条例の前文でうたっているのは、前文に指摘されたような種々の困難な課題を、市民活動の活性化を通じて解決しよう、解決の糸口を見いだしていこうということです。従って、社会状況の変化がないことを前提としているのではなく、逆に変化させることを目的にしています。
なお、前文中に示す課題は市民にとって身近で具体的な課題の例を示すものであり、一人でも多くの市民が市民活動に取り組むきっかけになることを願っています。なお、今日的状況を前文に記載した例として、男女共同参画社会基本法や少子化対策法などがあげられます。
男女共同参画社会基本法 前文 平成11年6月23日法律第78号
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
少子化社会対策基本法 前文 平成15年7月30日法律第133号
我が国における急速な少子化の進展は、平均寿命の伸長による高齢者の増加とあいまって、我が国の人口構造にひずみを生じさせ、二十一世紀の国民生活に、深刻かつ多大な影響をもたらす。我らは、紛れもなく、有史以来の未曾(ぞ)有の事態に直面している。
しかしながら、我らはともすれば高齢社会に対する対応にのみ目を奪われ、少子化という、社会の根幹を揺るがしかねない事態に対する国民の意識や社会の対応は、著しく遅れている。少子化は、社会における様々なシステムや人々の価値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立った不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。急速な少子化という現実を前にして、我らに残された時間は、極めて少ない。
もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、こうした事態に直面して、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備し、子どもがひとしく心身ともに健やかに育ち、子どもを生み、育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し、少子化の進展に歯止めをかけることが、今、我らに、強く求められている。生命を尊び、豊かで安心心して暮らすことのできる社会の実現に向け、新たな一歩を踏み出すことは、我らに課せられている喫緊の課題である。
ここに、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。
質問: 少子高齢化や高度情報化の進展「進展」は進歩発展することなので、少子高齢化の進展とは言わないのではないでしょうか。また、一連の負の列記の中に高度情報化はなじまないのではないでしょうか。
回答: いずれの場合も、「進展」という言葉は、政府の公式文書でも、マスコミや研究者の記述でも日常的に使われています。男女共同参画社会基本法の前文にも「少子高齢化の進展」とうたわれており、一般に定着した表現と考えられます。
なお、少子高齢化、高度情報化ともに、マイナスやプラスの一方だけでなく、両面を合わせ持っていることはよく知られており、違和感を感じさせることはないと考えます。
質問: 前文に総合計画の文言が引用されていますが、総合計画が変わるたびに条例も変更するのでしょうか。
回答: 前文の文言は、総合計画に記されているからということではなく、その内容が相当長期にわたって本市の目標に掲げるにふさわしいとの考えから、条例検討委員会が選んだものです。したがって、総合計画が変わるたびに変えるということではなく、時代の大きな変化や推進委員会からの施策の改善意見等をふまえて適切な対応を図ってまいります。
質問: 現状を踏まえるのに、「社会全体の急速な少子高齢化や~省略~世界平和への不安など」と、ここまで羅列する必要があるのでしょうか。
回答: 市民活動を推進する理由は、本来の自治の姿であるはずの市民協働の推進です。
そのためには現在の社会情勢を共通の認識として真剣に受け止める必要があると考えております。
質問: 「志を持った」という表現により、持つものと持たないもので差別的な捉え方をされる恐れがあるのではないでしょうか。
回答: 現在の社会情勢と今後のあり方を考え、強く願うこととして表現した文言であり、差別的な意図はありません。市民協働を実現するために市民活動はなくてはならない存在ですが、市民活動に対する誤解や偏見が未だ社会の認識の中で存在していることも事実です。この文言は、自主的・自立的である市民活動を推進するために、市民活動を行うものの姿を表現するものとして必要な文言と考えております。
質問: 市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が協力して行うことを単に「協働」とはいわずに「市民協働」とした理由は何でしょうか。
回答: 同じ協働であっても、これまで一般に見られた行政主導型から脱却して、市民が中心の協働でなければならないという点を強調する意味で、あえて「市民協働」と名付けるのが適当と考えました。全国の多くの自治体で「市民協働」と呼んでいるのも、同じ理由と考えられます。
目的
第1条 この条例は、市民活動の推進に関する基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、市民活動が活発に展開される基盤を整え、もって市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が互いに良きパートナーとして協力しあう、市民協働による真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
趣旨
本条は、本条例の目的を明らかにしたのもであって、解釈の指針となるものである。
解説
真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現には、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が社会における役割を認識した上で公共を実現する必要があるため、この条例の目的としたものである。
1 パートナー
パートナーとは、「違いを認め合うこと」、「対等であること」、「互いの合意のうえで役割分担すること」を前提とするものである。
2 市民
市民とは、綾瀬市に在住、在勤、在学及び事務所または事業所を有する個人並びに綾瀬市に利害関係を有する者である。
3 市民活動を行うもの
市民の中で市民活動に直接的に携わる個人または団体をいう。
Q&A
質問: 「市民協働」と「市民活動」の関係はどのようなものでしょうか。
回答: 市民協働はまちづくりを行う上で不可欠なものであり、市民活動を推進することにより最終的に成し得るものと考えております。並列で規定することも条例検討委員会で話し合われましたが、条例全体をわかりにくくするため、本条例では市民協働を市民活動の高次的目的として整理しております。
定義
第2条
- この条例において「市民活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした自主的かつ自立的に行う活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動。
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。
- この条例において「事業者」とは、営利を目的とする事業を営む個人及び法人をいう。
- この条例において「市民協働」とは、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、互いに良きパートナーとして連携し、それぞれの特性及び持てる力を生かし合って協力することをいう。
趣旨
本条は、本条例で用いる基本的な用語である「市民活動」、「事業者」、「市民協働」の定義を明らかにしたものである。
解説
1 市民活動
市民活動の概念には、市民の自主的な参加と支援によって行われるあらゆる自発的活動である「広義の市民活動」と、その中で、社会的課題の解決に向けて自主的かつ組織的、継続的に行われる「狭義の市民活動」が存在する。その定義についてはこれまでも議論されてきたが、生涯学習都市宣言などに代表されるような様々な施策により、「広義の市民活動」が推進されてきていることを鑑み、本条例でいう市民活動は「狭義の市民活動」を指す。
2 宗教・政治活動の制限
特定非営利活動促進法第2条第2項二と同義である。
3 事業者
営利を目的とする活動を行う者をいい、事業を行う個人のみならず法人を含む。
4 市民協働
市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が、その自主的、自立的な行動のもとに、良きパートナーとして連携し、それぞれの知恵と責任においてまちづくりに取り組むことをいう。
Q&A
質問: 市民活動の定義が抽象的であり、具体的に明記できないでしょうか。
回答: 市民活動とは、一般的に「非営利の社会貢献活動」や「市民公益活動」とも言われ、ボランティアや環境、福祉、教育などさまざまな場面で、市民が互いに協力し、問題や課題に自主的、自立的に取り組む、公共の利益に寄与する活動を指します。その活動は条例案各号の事項を除き、範囲や形態に制限はなく、今後も様々な形で誕生してくるものと考えられます。このような意味を含め条例上最低限の要件を満たすものとして表記しています。なお、市民活動の定義については、特定非営利活動促進法や既に制定されている他市の定義を参考にしています。
質問: 具体的にどのような活動があるのでしょうか。
回答: さまざまな活動があり、NPO法上では分類を17区分しています。平成16年1月現在、県内では889団体が認証を受けており、そのうち30%が保健・医療・福祉分野で、20%が子どもの健全育成、社会教育となっています。この条例では将来的に生まれる新たな活動も含めるため、さらに広い範囲が対象となると考えます。
特定非営利活動促進法 平成10年3月25日法律第7号
別表(第二条関係)
- 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 二 社会教育の推進を図る活動
- 三 まちづくりの推進を図る活動
- 四 観光の振興を図る活動
- 五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 七 環境の保全を図る活動
- 八 災害救援活動
- 九 地域安全活動
- 十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 十一 国際協力の活動
- 十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 十三 子どもの健全育成を図る活動
- 十四 情報化社会の発展を図る活動
- 十五 科学技術の振興を図る活動
- 十六 経済活動の活性化を図る活動
- 十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 十八 消費者の保護を図る活動
- 十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
質問: 生涯学習や趣味の活動は市民活動に入らないのでしょうか。
回答: 市民活動には、趣味的活動を含む市民がかかわる活動全てを示す広義の市民活動と、NPO法で特定非営利活動と呼ぶような公益性の高い狭義の市民活動があります。
広義のいずれの市民活動も大切な活動ですが、文化サークルやスポーツサークルなどは、市民一人ひとりの趣味や価値観に基づいて行われるものです。行政が支援のためとはいえ個々の活動の善悪や軽重を判断するのは適当ではないと考えます。
本条例は、社会貢献活動としての市民活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。また、前文に掲げたような厳しい社会の現実認識に立っていることとや、こうした分野の市民活動がわが国全体で活発ではなく、早急に活発化させることが公益に合致するという考えから、個人や構成員相互の利益(共益的)を目的とした活動については対象としません。
質問: 市民活動の範囲がわかりづらいので市民協働活動としてはどうでしょうか。
回答: 「市民協働活動」と呼ぶ場合は、市民活動の中からさらに行政等との「協働」が行われているものに限定することになります。先進市においてもそうした実例は極めて少なく、条例によって協働の重要性を訴え、まず市民活動の活発化を図り、その成果として市民協働が数多く実現する。というのがこの条例の意図するところです。
質問: 現在、市民活動団体は市内にどのくらいあるのでしょうか。
回答: 平成16年2月末日現在で、市内NPO法人の認証を取得した団体は8団体あります。その他法人の認証を取得しないで活動している団体については、社会福祉協議会のボランティア連絡会の加入団体など、何らかの関係で行政と関わりのあるものについてはある程度把握できますが、この他に多くの市民活動団体があるものと考えています。なお、平成13年度市民活動団体の実態調査を行った際に対象とした団体数は99団体でした。
質問: 第2条第1項の規定は、何に基づいて規定されているのでしょうか。
回答: 特定非営利活動促進法平成12年4月施行、NPO法)の第2条に規定されている「特定非営利活動」の規定から準用しています。
特定非営利活動促進法 平成10年3月25日法律第7号
定義
第二条
- この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
- この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
- 一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
- イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
- 二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
- イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
- 一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
質問: 第2条第1項「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」とはどのような意味でしょうか。
回答: 「不特定かつ多数のものの利益」とは「公益」と同義で、「社会全般の利益」を指すものと解され、受益者が特定されてはならないことを意味します。従って、「私益」(特定の個人や団体の利益)、「共益」(構成員相互の利益)は除かれます。
質問: 第2条第2項「営利を目的としない」とはどのようなことでしょうか。
回答: その活動が対価を受けとっているかどうかということだけで営利か非営利かを判断するのでなく、その活動によって得られた利益や資産を構成員に分配していないことを言います。
質問: この条例で営利を目的としない事業者はどこに位置付けるのでしょうか。
回答: 「営利を目的としない事業者」という表現は法律では皆無ですが、本条例で想定しているのは、第一にNPO法人等市民活動団体です。これらについては「市民活動を行うもの」に位置づけられます。社会福祉法人や学校法人、自治会、組合などが法人または組織として市民活動に参画する場合も、「市民活動を行うもの」と位置づけます。なお、条例案に「市民活動を行うもの」したのは、市民活動団体以外にも市民活動を行うさまざまな組織があることを想定しているためです。
質問: 除く活動とされている政治・宗教活動とはどのようなものでしょうか。
回答: NPO法に定義されている内容と同様であり、政治活動については、政治上の主義(政治によって実現しようとする基本的、恒常的、一般的な原理・原則などの推進についてを除く活動としており、政治上の施策(政治によって実現しようとする比較的具体的なもの)は認められています。
宗教活動については、憲法20条に規定されているとおり自由を保障されており、本条例による市からの財政的支援等を行うことは憲法89条で制限されているため除いたものです。
質問: 「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動。」の判断はどのようにするのでしょうか。
回答: いずれもその制限は主たる活動とする団体に限られ、従たる目的として行うことは差し支えないとされています。
また、この条例に規定される施策の受益者としての団体については、個別に判断が必要であり、その判断が困難な場合は、推進委員会で検討していきます。
なお、本条例では、団体自体の活動に制限を加えるためのものではないため、ここで定める事項は、既に宗教法人法や政治資金規制法など既にその団体について法的に立場を保障されている団体以外の団体が対象となります。
質問: 政治上の主義に関することをなぜ除くのでしょうか。
回答: 政治上の主義に関わることを「主たる目的」とする市民活動を行政が支援するようなことになれば、行政に恣意的に利用される危険性が憂慮されるためです。
質問: 市民活動団体に地縁組織は含まれるのでしょうか。
回答: 地縁組織の代表的なものに自治会があります。自治会は一定の地域の人で組織する相互扶助活動(共益)を中心とした団体であるため、本条例にいう市民活動の範囲には含まれないと考えます。ただし、自治会がまちづくりや環境を守る活動など本条例に示す活動を行う場合は、市民活動を行うものとして捉えてよいと考えます。また、本条例は、法の置付けや社会的認知が未成熟な小規模な市民活動も含め推進する目的で制定されるものであり、自治会については、既に地方自治法で法人化について選択の余地があり、市の補完的役割から財政的支援も得ている状況を鑑みると、必ずしもこの条例で規定する市民活動の枠に当てはめることは適当でないと考えます。
基本理念
第3条
- 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市は、市民協働によるまちづくりの重要性と、市民活動が真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現に欠くことのできない重要な役割を担うことを深く認識し、創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性その他市民活動の持つ特性を尊重し、互いの理解と信頼を基礎に市民活動の推進を図るものとする。
- 市民活動の推進に当たっては、自発性、自主性及び自立性を最大限に尊重するとともに、公開性と透明性を基本として互いに情報の共有に努めるものとする。
趣旨
本条は、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が市民活動を推進するに当たっての基本理念を定めたものである。
解説
第1項では、真に豊かで魅力と活力あふれる地域社会の実現のために、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が相互に重要な役割を担うことを認識するとともに、相手の特性を充分に理解・信頼し市民協働によるまちづくりと市民活動を推進する重要性を認識することを定めたものである。
1 市民活動の持つ特性
主に行政との対比として一般的に用いられているもので、これらは、行政や事業者と市民活動を行うものとを比較し優劣について意味するものではない。
それぞれの特性(行政は公平・平等を旨として画一的・一律的な対応を求められ、しかも全体を考慮した上で優先順位を決定しなければならない。事業者は営利を追求し、得た利益を税金として収め社会に還元する)を尊重し、不足を補い、互いに高めあいながら市民活動を推進する必要がある。
第2項では、市民活動を推進するに当たり、活動の公開性と透明性を基本とし、相互に情報の共有化に努めながら、市民の自発性と市民活動を行うものの自主性、自立性を尊重することを規定したものである。
市民活動の内容、状況を誰でもが情報として知ることが出来るように積極的に公開することにより、市民活動に対する理解が深まるものとの考えである。また、特に行政の一方的な制度・政策の押し付けや、市民に対して強制的な市民活動への参加・参画を抑制したものである。
市民活動を行うものの役割
第4条
市民活動を行うものは、基本理念に基づき、市民活動の持つ社会的意義とその活動に伴う責任を自覚するとともに、開かれた運営を通じて当該活動への市民、事業者及び市の理解及び参加・参画の推進に努めるものとする。
趣旨
市民活動の推進主体である、市民活動を行うものの役割を規定したものである。
解説
市民活動を行うものは、市民活動の主体として、その社会的意義と責任を自覚し、自らの責任のもとに活動の公開性と透明性をもって、市民、事業者等の理解及び参加、参画に努めるものである。
1 市民活動の持つ社会的意義
その特性を生かし社会的課題を解決することであり、現在一般的に社会的課題として認知されていないものも含む。
2 参加・参画
「参加」とは、団体または事業に加わることであり、「参画」とは、企画・立案及び決定の場にも加わり負担・責任も担い合うことを意味する。
Q&A
質問: 市民活動の持つ社会的意義とは何でしょうか。
回答: 市民活動の最大の意義は、生活者の視点から問題点を発見し、国や自治体などとは違った視点や価値観から解決策を提案したり、前例や職務分掌、定められた予算などに縛られることなく、柔軟に行動に移したりできる点にあると考えられています。
前文に掲げられたような新しい、さまざまな課題の解決に向かって、きわめて重要な役割を担っているといえます。
市民の役割
第5条
市民は、基本理念に基づき、市民活動の意義と重要性に対する理解を深め、強制されることのないそれぞれの自由で自発的な意思によって市民活動に参加・参画し、あるいはその発展に協力するよう努めるものとする。
趣旨
市民活動の推進主体である、市民の役割を規定したものである。
解説
まちづくりの主体としての市民に対する理解を深め、積極的な市民活動への参加・参画又は、協力を規定したものである。しかしながら、市民の市民活動への参加・参画・協力は、あくまで強制でなく、任意の努力規定とした。
市民活動を広く市民や事業者に理解してもらい、参加・参画を促進して行くために、活動するものが責任と自覚を持つとともに、その活動内容を積極的に公開して行くことが必要である。
事業者の役割
第6条
事業者は、基本理念に基づき、地域社会の活性化と健全な発展を担う重要な一員であることを認識し、市民活動に対する理解を深めるとともに、その推進に積極的に努めるものとする。
趣旨
市民活動の推進主体である、事業者の役割を規定したものである。
解説
事業者は、市民活動の推進主体であることを認識し地域社会の一員として、市民活動を理解するとともに、本来の行動原理である経済活動だけでなく、市民活動の健全な発展のため、寄付金や助成金等の金銭的支援にとどまらず、場所の提供、備品の貸し出し、技術的指導・ボランティアの派遣など、さまざまな方法で市民活動の推進に積極的に努めることが重要である。
ただし、あくまでも事業者の取組みについても、強制でなく自発的なものでなければならない。
市の役割
第7条
市は、基本理念に基づき、市民活動の推進に関する施策を策定し、実施するよう努めるものとする。
趣旨
市民活動の推進主体である、市の役割を規定したものである。
解説
市は市民活動の推進のため、市民活動を行うものからパートナーとして積極的な参加・参画を得られるよう、適切な施策の実施に努めることを規定したものである。なお、必要な施策(第8条で規定)は策定し、実施するよう規定したものである。
Q&A
質問: なぜ「市の責務」とせず「市の役割」としたのでしょうか。
回答: 市民協働においては互いに対等であることが基本であることを鮮明にする狙いから、市民等と同じく「役割」としましたが、市民活動を推進するためには、公益活動の多くを担う市の役割が非常に大きいともいえますので、条例第8条ではその具体的施策を事実上の市の責務として規定してあります。
市の施策
第8条
前条に規定する施策には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 市民活動の場及び活動支援の拠点づくりに関すること。
- 財政的支援及びその仕組みづくりに関すること。
- 市が行う事業への参入及びその仕組みづくりに関すること
- 情報の収集、提供及びその仕組みづくりに関すること。
- 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市の連携並びに相互交流の推進に関すること。
- 市民活動への積極的な参加と支援を促すために必要な啓発及び仕組みづくりに関すること。
- 職員に対して市民活動に関する啓発及び研修を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項
趣旨
本条では市が市民活動を推進するために行う施策を、具体的なものとして列挙したものである。
解説
1 市民活動の場及び活動拠点づくり(第1号)
市民活動を行うもののそれぞれの活動を恒常的に行うための場づくりは、市民活動の推進に必要不可欠なものであるとともに、団体間の交流の促進や市民への啓発効果についても期待できるものであり、市民活動サポートセンターの設置など活動の拠点づくりに努めていくものである。
2 財政的支援及びその仕組みづくり(第2号)
市民活動は本来、自主自立を基本とし、その活動を行うこととしている。しかしながら、市民活動を行うものの一番の課題は、資金調達でもあり、市民活動の推進のため、財政的支援の仕組みづくりを行うものである。
3 市が行う事業への参入及びその仕組みづくり(第3号)
市民活動を行うものの多くは、法人格を持たないものがほとんどであり、法人格の有無に関わらず、行政サービス事業への参入機会や業務委託などの仕組みづくりを行うものである。
4 情報の収集・提供及びその仕組みづくり(第4号)
市民活動を行うものと、市民、事業者及び市の市民活動に関する情報の収集、提供を行うための仕組みづくりを行うものである。
5 市民活動を行うものと、市民、事業者及び市の連携並びに相互交流の促進に関すること(第5号)
市民活動を行うもの、市民、事業者及び市が、それぞれが持つ特性、機能等を発揮した中での、連携した市民活動は単体で行う時より、より多くの効果が得られることから、連携や相互交流を推進するものである。
6 市民活動に関する市民及び事業者の理解を深め市民活動への積極的な参加と支援を促すために必要な啓発及び仕組みづくり(第6号)
市民活動に対する市民及び事業者の理解が、まだ十分とは言えない状況であり、市民活動を深く理解し、自発的参加と支援が行われるよう仕組みづくりを行うものである。
7 市職員に対して市民活動及び市民協働に関する啓発や研修を行うこと(第7号)
職員に市民活動の重要性を認識させ、市民活動を積極的に推進するための研啓発・研修を行うものである。
8 前各号に掲げるもののほか、市民活動の推進に関し必要な事項(第8号)
上記各7号の他、時代の趨勢や市民活動の変化により必要事項が生じた場合に、対応するものである。
Q&A
質問: 市の具体的施策はどのように決められるのでしょうか。
回答: 具体的施策については、条例第9条に定める推進委員会において検討されます。
第1号関係
質問: 市民活動の場及び活動支援の拠点とは具体的に何を指すのでしょうか。
回答: 市民活動を行うものが自由に集い、打合せや活動の準備などを行うスペースを有し、活動に必要な情報の入手や、活動の相談・支援を受けることのできるいわゆる市民活動サポートセンターを指します。なお、設置については推進検討委員会からの提言に基づき、既存の公共施設の活用を視野に入れながら条例制定後設置される推進委員会において具体的内容を検討してまいります。
質問: 現在市民活動を行う団体は主にどこで活動しているのでしょうか。
回答: 公民館をはじめコミュニティセンター、自治会館など地域の公共施設でその活動を行っている団体が多いと思われます。
第2号関係
質問: 財政的支援及びその仕組みづくりとはどのようなことでしょうか。
回答: 市民活動団体の財源については、自らの会費によるものが大半で、次に行政機関等からの補助金等が主要な財源であると考えられています。その内容は、事業への支援や団体発足時の支援などが挙げられ、財源としては、市からの直接補助をはじめ、基金・公益信託などさまざまな方法があります。
また、市民活動推進検討委員会に提言されたような、サンセット方式の導入による有期限での支援や公開プレゼンテーションによる平等な決定過程も視野に入れながら、推進委員会による充分な議論による制度化が必要です。
質問: 既存の補助金の見直しが必要でしょうか。
回答: 平成15年度市から131団体に補助金が交付されていますが、運営費補助をはじめ事業補助や建設費補助などその内容はさまざまです。これらが市民活動を行う団体かどうかを判断するためには、運営内容をはじめ補助を受ける経過や施策としての意義を詳細に検討し判断する必要があります。
また、団体への補助金交付については行政改革専門部会の意見に基づく補助金等見直し基準により見直しを図ってきている段階であり、市民活動の理念が定着していない現段階において既補助団体の公益・共益性、自主性、施策としての支援の必要性や支援方法等を判断することは妥当ではないと考えるため、まずは新たに支援を受けるものを対象とした制度による支援を優先し、市民活動の成熟度に応じて既交付団体との整合性、既存の補助金の見直しを図ることが必要と考えます。なお、条例制定時は、新たに支援を受けるものを対象とした制度による支援を優先し、市民活動の成熟度に応じて既交付団体との整合性を図ります。
第3号関係
質問: 市が行う事業全てに市民活動団体が参入するのでしょうか。
回答: 本規定は、市が行う行政サービス事業全てに市民活動団体の参入の機会を提供する意味ではなく、市民活動を促進するとともに、多様な行政サービスを柔軟に供給することなどが目的のため、市民活動団体に委託する意義を考慮した上で市が積極的に工夫して取り組む必要があります。よって、対象となる事業は市民活動の特性である創造性、先駆性、専門性、多様性、柔軟性などが生かさせる分野に限られます。
また、先進市でも事例が少なく、事業を委託する場合には、法人格の有無にはとらわれないが、受託者としての権利義務が生じるため、その仕組みについては推進委員会において十分な検討が必要と考えております。
第4号関係
質問: 情報の収集、提供を行うための仕組みづくりとはどのようなものをさすのでしょうか。
回答: ホームページ上での電子会議室の設置やメーリングリストによる情報の配信を代表とする電子情報を活用した情報収集や提供など、市民活動を行うもの、市民、事業者及び市の情報の共有と市の積極的な情報提供の方法について示すものであり、内容については市民活動推進委員会で検討いたします。
第7号関係
質問: 市役所職員を対象とした研修はどのように進められるのでしょうか。
回答: 市民活動を推進する上で、職員の意識向上は非常に重要なことであり、条例制定後にその位置付けを協議していきます。なお、市民活動への理解を促進させるために、昨年度から現在の職員研修制度の中で、職責毎に研修を実施しており、今後も段階的に実施していく予定です。
市民活動推進委員会
第9条
市民活動の推進に関する施策その他の事項について、市長の求めに応じて調査審議し、その結果を報告し、及び市民活動全般に関し必要な事項について意見を述べるため、綾瀬市市民活動推進委員会(以下 「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、毎年度、市民活動の実情及び施策の改善を必要とする事項等について報告書を市長に提出するものとする。
趣旨
市民活動及び市民協働の推進に関する施策その他の事項について、調査審議するとともに、その他必要事項について意見を述べるため市民活動推進委員会を設置する。
解説
第1項は、市長からの諮問に応じ調査・審議する機能のほかに、委員会が建議できる規定を設けることで、自発的かつ自由な議論を尊重し、その位置付けを保障するために設けた規定である。なお、委員会は地方自治法第138条の4第3項に基づく市の附属機関である。
第2項は、市民活動の実情を年度単位で把握し、施策の改善策等を調査審議し市長に報告書を提出することで、その推進に資するものである。
Q&A
質問: 市民活動推進委員会はどのような機関なのでしょうか。
回答: 地方自治法第138条の第4第3項の規定(「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関として中略、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査のための機関を置くことができる。」)による附属機関です。
質問: 市民活動推進委員会の組織はどのように規定していくのでしょうか。
回答: 市民活動推進委員会規則を定めその中で、委員会の組織、運営等(趣旨、所掌事務、委員、会議)詳細を規定します。これは条例が理念を定めたものであり、委員会の詳細を定めるのになじまないことと、今後の市民活動の変化に対応し易いよう規則で規定したほうが望ましいと考えたからです。
質問: 委員会の選出区分や人数は決まっていますか。
回答: 委員は2年の任期で、委員数15名以内とし、市民活動を行うもの(2から4)、公募による市民 (4から6)、事業者(2から3)、学識経験者(2から3)、市の職員(1から2)を想定しています。
質問: 市の附属機関であり諮問機関である委員会に市職員を含めるにはなぜでしょうか。
回答: この委員会は市民活動を推進するための調査審議と、市民活動に必要な意見を述べるために設けられたもので、市民活動を行うものと、市民、事業者及び市が良きパートナーとして委員会を構成し、それぞれ四者が同じ委員としての立場での意見交換をする必要があることから、市の職員を委員として位置付けました。
委任
第10条
この条例に定めるもののほか、市民活動に関し必要な事項は、別に定める。
趣旨
この条例に基づく市民活動に関して必要な事項は、別に定めることを規定したものである。
解説
市民活動に関して必要な事項は、必要に応じ規則・要綱等により別に定めることを規定したものである。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
Q&A
質問: 条例検討委員会からの案には、附則に条例施行後5年を目処に検討を加えることとなっていましたが、その項目が除かれているのはなぜでしょうか。
回答: 委員会では条例施行後の社会情勢の変化や市民活動の新たな伸展などにより、この条例を積極的に見直すために、5年を目処に検討をすることを規定しましたが、第9条2項の規定により、市民活動推進委員会により改善の検討が行われることを考慮して条文から除きました。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0467-70-5640(市民共創)、 0467-70-5657(多文化共生)
ファクス番号:0467-70-5701
お問い合わせフォーム(市民共創)
お問い合わせフォーム(多文化共生)
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


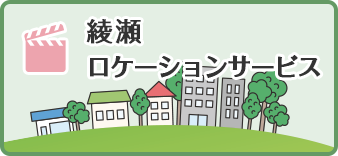
更新日:2023年02月01日