令和7年度文化財企画展「蓼川谷戸講中の講中膳椀及び帳簿類一式」指定記念 新指定文化財と綾瀬の講中道具
新たに指定された市指定文化財を紹介する展示を行います!

文化財企画展(チラシ)
令和7年3月に新たに、蓼川谷戸講中で使用されていた共有の膳椀類及び帳簿類一式が市の指定文化財に指定されました。
指定を記念して、蓼川谷戸講中の講中膳椀及び帳簿類を、指定に至った理由やこれらの道具が語る意義について展示します。
展示では、講中とはなにか、膳椀とはなにか、なぜ地域の人々が共有で道具を所有していたのかといった背景についても展示しますので、はじめて講中文化や膳椀類を知る方でも安心してご見学いただけます。
綾瀬市域全域で行われていた、互助協働組織である「講中」について触れてみませんか。
蓼川谷戸講中とは?

蓼川谷戸講中から寄贈された資料
蓼川谷戸講中は、現在の蓼川1丁目から3丁目の家々で構成されていた互助協働を目的とした組織です。
蓼川谷戸講中で使用されていた、特別な行事の時に使う豪華な食器類や、それらの借り方・購入履歴などが書かれた帳簿類がまとめて綾瀬市に寄贈され、その重要性が評価されて市の指定文化財に指定されました。
講中とは?

蓼川谷戸講中の講中膳椀
講中(こうじゅう)とは、助け合いを目的に地域の人々が集まって作った、互助協働組織です。今でいう自治会のようなものですが、結婚式や葬式の対応、集落内の道路や水路の維持管理など様々なことを講中の人々と行っていました。
※講中には、他に、信仰に関わる講中もあります(例:地蔵を祀る地蔵講、不動尊を祀る不動講など)。綾瀬市域周辺では、「講中」には、信仰の集まりと互助協働組織の集まりの2つの種類があったのです。
【なぜ講中が必要だったの?】
江戸時代から昭和時代初めころまで、現在のように、トラブルがあった際に対応する市役所や、冠婚葬祭を行う専門業者はありませんでした。そのため、地域の運営や整備、冠婚葬祭などは自分たちで行う必要がありました。
各家々だけではこれらの対応ができないため、数軒の家で協力して対応に当たっていたのです。また、冠婚葬祭などの特別な行事で使う道具は、今も昔も高価なものが多く、1つの家で購入することはなかなかできませんでした。そこで、数軒の家々でお金を出し合い、共有で購入したのです。
このように、今とは異なる社会体制の中で、地域を運営し、人生の節目の行事を行うために互助協働組織である講中が必要だったのです。
~展示の詳細~
| 日時 |
8月4日(月曜日)から24日(日曜日)9時から16時まで ※8月4日(月曜日)は13時~16時 [8月11日(月曜日・祝日)はお休みです] |
| 場所 |
市役所7階市民展示ホール |
| 内容 |
【第一章】 新指定文化財 蓼川谷戸講中の講中膳椀及び帳簿類一式 1. 指定文化財について 2.蓼川谷戸講中の講中膳椀及び帳簿類一式について
【第二章】綾瀬の講中道具 市内で調査が実施され、市に寄贈されている資料を紹介します。 1.市内の講中文化について 2.市内の講中道具について
【ミニコーナー】 1.蓼川の歴史―厚木基地と人々の暮らし 2.明治から昭和にかけての綾瀬 |
|
展示 解説 |
・8月10日(日曜日):10時~11時、14時~15時 ・8月24日(日曜日):10時~11時、14時~15時 ー当日受付・直接会場へー |
| 特別講座 |
日時:8月23日(土曜日):11時~13時(質疑応答・休憩含む) 場所:綾瀬市役所 3階314・315会議室(10時30分開場) 内容:1神奈川の共有膳椀について、2蓼川谷戸講中の講中膳椀について 講師:1桜美林大学非常勤講師 加藤 隆志 氏 2綾瀬市文化財保護委員 小川 久治 氏 ※講師について:事前に配布されている市広報及びチラシ等に掲載されていた講師から、講師が変更になっています。ご了承ください。
◎参加ご希望の方は、電話・メール・電子申請で、生涯学習課へ申込ください。定員に空きがある場合は、当日参加も受付となります。 申込先:電話 0467-70-5637(直通) メール wm.705637@city.ayase.kanagawa.jp |
◎協力:綾瀬市史跡ガイドボランティアの会、綾瀬文化財調査会

特別講演会申込フォーム
電子申請申込先
左のQRコードを読み込んでお申し込みください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


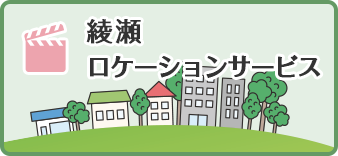
更新日:2025年08月01日