令和6年度第1回綾瀬市文化財保護委員会(令和6年7月17日開催)
審議会等の名称
令和6年度第1回綾瀬市文化財保護委員会
開催日時
令和6年7月17日(水曜日) 午後1時30分~午後3時
開催場所
綾瀬市役所 6階 教育研究所研究室1
議題
諮問
(1)文化財の取扱い基準について
議題
(1)文化財の取扱い基準について
(2)市指定文化財について
(3)その他
・文化財保存活用地域計画について
・令和6年度文化財関連事業について
出席者
委員 *会長◎ 副会長○
◎矢島 國雄 加藤 隆志 中武 香奈美
事務局等
市民環境部長、生涯学習課長 他3名
傍聴者数
0名
内容
内容は、要点報告です。
(会長)議題1「文化財の取扱い基準について」市長より諮問があったため、意見を取りまとめたい。詳細については事務局お願いします。
(事務局より説明)
(会長)文化財の取扱い基準について、大変難しい課題かと思いますが、委員の意見はありますでしょうか。
(委員) 本基準には、 1つは、すでにある既存資料をいかに整理していくのかという問題がある。もう1つは、新しい資料を収集する基準は何かということ。さらにもう1つ、資料を破棄せざるを得ない場合の破棄する基準は何か、という、すごく大きな基準が3つ入っている。例えば、栃木県立博物館は、令和3年に新収蔵庫を建て、新基準(「収集、保管、活用等に関する要綱」)を作った。この3つをきちんと整理しないと、基準として分かりづらい。分野によっても書きぶりがずいぶん違うところが出てしまっており、唐突な感じがするところもある。
また、現在、大きなニュースになっている唯一の民俗の専門の博物館である、奈良県立民俗博物館。知事が変わって、前任の方針を全部ひっくり返して、4万数千点の民俗資料があって、置く場所が無くて、再編整理をしないといけない。そこまではいいが、すでにあるものを破棄するという判断をトップがやっている。破棄しなければいけないことはありえることだが、そこで、知事が、「県民が言われるままに何も基準がなく集めた結果がこうなったんだ」ということを言ったと新聞報道にあった。しかし、集めたのは行政であって、むしろ我々の時は全国的に一生懸命集めなさいよと言われていた。系統だってなるべくたくさんのものを集めることによって、地域の文化を明らかにしようとした。むしろ忠実に選別をやった結果である。なにを言いたいかというと、やむをえず捨てるとか破棄することがよしんばあるとして、いままで集めすぎたとか、置き場所がないから破棄するんだという書きぶりはまずいし、してもらいたくない。今までの経過や歴史を含めたうえで、今後どのように積み上げていくのかを、書いてもらいたい。もう1つが、実際に破棄、再整理をする場合、そのスケジュール感、いつごろまでにだれがどういう整理をするのか、というのをある程度見通しをたてないと、結果いままで通りになってしまう。具体的なスケジュール感を背景としてもっていないと、このまま終わってしまうのではないかと危惧をした。
(委員)前回のものより見やすくなったなという感じはする。ただやはり、他の委員が言うように、項目のレベルが違うものがある。突然、具体的な内 容が入ってきたり、大きな項目があったり、いるかなあというところはある。市史編集審議会で出された歴史的公文書の基準でも、レベルが違うので、総則と細則に分けた方がいいかもしれないという意見が出ており、私もそういうふうに思った。より具体的な例があったほうが実際に携わる人が混乱しないが、具体的な項目ばかりにしていると項目がずいぶん増えてしまい、おさまりが悪い。なので、もう少し、絞ってもらえるといい。
また、質問だが、「文化財資料の調査・収集」の3、「寄贈者の置かれた状況から判断し、寄贈をうける」というのが、意味がよくわからない。あまりにも劣悪な状況に置かれている資料を市役所のほうで保管するということでしょうか。
(事務局)綾瀬市では、収蔵庫にこれ以上入らないので、基本的には受け付けないような姿勢を今後も続けていかざるをえないと思う。ただその中でも、所蔵者の方で、多量の文書等をもっていらっしゃる方がいて、“もう自分のところで置いておけないので、手放したい、捨てたいけど、重要だといわれているからできるだけ綾瀬市に寄贈したい”といってくださっている。そういう場合に、所蔵者の所蔵環境を鑑みて、これ以上所蔵が難しい資料のみ寄贈を受けるという考えである。収集という基準をつくっても、置いておく場所が無ければ収集は進まない。だが、なくなる前に保存しないといけない資料もある。それはもう何をしてでも、どうにかして場所を確保して寄贈をうけて、資料の散逸を防ぐというために、寄贈という文言をここに入れた。
(委員)“資料がこのままだと捨てられるかもしれない”というところだったら、何とかして受け取るということですね。その収蔵場所は、どうにかするということですね。他の委員が言ったように、実際に処分をして、スペースを空けて、新しく受け入れる基準を作って、それだったら、受け入れざるを得ないということになりますよね。そういうことをするとなったら、やはり、収集する基準は、収集が可能か、可能じゃないかではなく必要だと思う。いっぱいだから収集しないのは、奈良県知事と同じである。なお、収集と“処分をしてある程度のスペースを空ける”のは、分けて考えた方がいい。分けないと、集めることができなくなる。
それから、寄託についてだが、収蔵場所を確保する課題はあるが、検討する対応をしてほしい。
7番については、「歴史全般」にして、近現代史は、綾瀬市の歴史の特徴であるので、難しいかもしれないが「軍関係資料」とするとうまく収まると思った。近現代史と歴史の項目が重複しているのは違和感がある。
(事務局)近現代資料は、扱う側としては区別をしておきたいと思うが、分けない方がいいか。
(委員)近現代史となると対象が広くなる。軍だけではなくなる。
(委員)やるのであれば、“歴史”の項目のなかに「特に旧日本軍に関する近現代資料は」というように付け加えればいいのではないか。基地関係資料は、紙資料だけじゃなくて、軍隊で使われた道具も入っている。そういった紙資料とそれ以外の切り分けをできないとすると、“歴史”のなかに、特に綾瀬市にとって重要な海軍や厚木(基地)のことについて、といれると、むしろそっちの方が目立つかもしれない。それは非常に理解がされやすい。
(事務局)承知した。
(会長)有形文化財には様々な資料が複数の項目に重複状態で入っているので、“歴史”でまとめておいた方がいいとも考えられる。また、指摘があった、項目のレベルがそろってないことについて、もう一段低い項目を造ってレベルを整理すると、全体としては見やすくなると思う。今日ここで全ての点をチェックするということは、作業的には不可能ではないが、委員が2名欠席しているため、10月までの期間に委員の皆様に意見を送っていただいて、各項目に対する意見を取りまとめて提出していただくことをお願いしていただけたらと思う。
文化財の取り扱いの基準の問題では、考古資料については、すでに1980年代に出土品の取り扱い基準というのが各自治体に求められており、考古資料については、地域性はあるものの、一応全国レベルでほぼ同様な取り扱い基準ができあがっており、運用されているという実態がある。
続いて、二つ目の議題2「市指定文化財について」。この件については、令和5年度の文化財保護委員会でお諮りをして、意見を取りまとめていた。その意見に基づいて、再度、対象文化財の検討を行ったと聞いている。詳細については事務局お願いします。
(事務局より説明)
(会長)この報告で、きちんとした調査報告になっている。他委員どう考えますか?(委員)19世紀の後半ころには、この周辺では、念仏講とか稲荷講の信仰的な講習慣があり、いわゆる冠婚葬祭に使う道具をそろえるとか、いわゆる地域の相互互助に関するまとまりのことを、南関東では講中といい、それが非常にたくさんできてくる。綾瀬でも一番古いのは、嘉永年間。いずれにしても、“セットで残って”おり、文書類があるので、何年ごろ、どういうものを作ったか使ったかが全部わかる。さらに、綾瀬にとって重要なのは、移転した地域の資料だということ。それから、市民ボランティアの成果であること。講中膳腕を指定にもっていったという例はあまり無い。東京都では、福生市が講中道具を東京都の指定文化財にした。その時に指定基準書を書いた人に書いてもらう方法もあるが、報告として充分であるためなくてもいいと思う。(会長)必要なことは書いてあるし、評価は明確に下されている。これを調査報告として、そのまま使わせていただければ、この委員会としては十分であると思う。
(委員)あとは市のほうで判断していただければ。
(会長)本委員会では、今回の調査報告をもって、評価はできていると判断させていただく。3番目は、その他について事務局説明をお願いします。
(文化財保護活用地域計画について、事務局説明)
(委員)文化庁の計画ですよね。最近では、伊勢原が作っている。伊勢原は日本遺産と一緒にやっており、大山めぐりの関係で町おこしの、地域振興に結び付けている。担当や文化財の委員会だけではなく、多様な、例えば商工関係とか観光関係とかも含め、役所全体での対応となる。何か核があるようなもの。綾瀬市でいえば、目久尻川と結びつけるイメージが必要。文化庁の認定を受けるには、結構大変だと聞くので、情報収集に努めて進めていく必要がある。
(会長)都道府県レベルでは、大綱をつくれと。各市町村は活用地域計画をつくれといっている。
(委員)本当は県の大綱を受けて市町村が作れということになっている。神奈川県はつくっているのか?
(事務局)神奈川県は大綱がある。
(会長)特に市町村は、なかなか文化財全部を見渡せるだけの専門の人が中にいると限らないので、手がつかないことが多い。それでも、はじめるなら、手伝うところは手伝う。
(事務局)かなり大変だといわれてはいる。しかし、ここで作らないとさらに文化財の崩壊は進んでいき、担い手は減っていく。境目にある。
(会長)いろんな庁内の関係するところと上手に協力していただかないといけない。
(事務局)承知した。
(令和6年度文化財関連事業及び文化財調査について事務局説明)
(事務局)資料以外に追加がある。昨年度市の指定を受けた道場窪遺跡の黒曜石の分析を明治大学の協力のもと、黒曜石センターで実施したため報告する。指定したものも、指定しっぱなしにはせずに、今後も調査・研究を進めていきたい。
(会長)(分析結果について追加説明)なお、分析は蛍光X線を使った非破壊の分析によるもの。学術的な報告はこれから追って、黒曜石研究センターとこちらとで相談して、最終的にどう発表するかは決める。とりあえずは、展覧会などの、この情報を使うことは承諾をもらっている。夏の展覧会にはこの情報が使える。以上。
(事務局)令和6年度の文化財保護委員会は、次回が2月。次回は、指定の諮問を市長から行う。
(会長)何か意見ありますか。
(委員)先ほど文化財関連事業の、“バカ面”のお囃子のお面を相模原に貸出しているとあった。この展示は、相模原市の番田にいた神代神楽という神楽師が解散し、使っていた道具を相模原市のほうに寄贈いただいて、市のほうで文化財にもっていくということでの紹介の展示である。ここと協力関係にあったのが厚木市の垣澤社中っていうのがあって、垣澤社中が明治のころに神楽を教わったのが、実は綾瀬の寺尾の本間平太夫という人である。本間平太夫は県央地区の神楽の中心を担っていた人です。教わった神楽は今も厚木で勢力的に行われている。そこで、関連があるため、綾瀬のも見てもらおうということで展示している。本間平太夫の資料は、この周辺の神楽師の人は、もっと市で資料は持ってないのかと注目している。多分出てこないと思うが収蔵庫を整理するとあるかもしれない。また、たぶん持っているお宅なんかもあると思う。見つかった折には、是非、収集して欲しい。非常に注目されている資料も綾瀬にはポツポツある。
(会長)ほかに何か意見等ありますか。質疑もないようですので、本日の議題につきましては、審議を終了いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


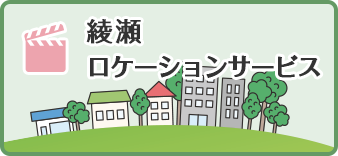
更新日:2025年01月31日