綾瀬ささら踊り
【ささら踊りの概要】
ささら踊りは、江戸時代中期に始まったとされる踊りです。短冊状に加工した竹(ささら)と太鼓を鳴らしながら、輪になって踊りました。市域の各地で踊られましたが、地域ごとに少しずつ違いがあったようです。広場や道、報恩寺の前など様々なところで大々的に踊られ、人々が楽しみにしている行事の一つでした。また、ささらを使って踊る「盆踊り」は、製糸工場などに働きに出ていた女性たちが地元に帰ってきて参加する特別な行事でもあったため、男女交際のきっかけの場でもあったといわれてます。
明治時代の終わりごろに踊る機会が減っていき、大正時代から昭和初期には市内全域で踊られなくなりました。その後、昭和51年(1976)に、寺尾と深谷の有志により復活され、現在は綾瀬ささら踊り保存会により伝承されています。

綾瀬ささら踊りの写真(報恩寺)

ささら踊りの道具(上:小太鼓、下:ささら)
ささら踊りの復活
一度中断されていた踊りはどのようにして復活したのでしょうか。
かつて市域の各地で踊られていた盆踊り(ささら踊り)を復活させたいと、寺尾に住んでいた近藤しょう作(※1)さんが立ちあがりました。明治時代後期に生まれた近藤さんは、幼いころに聞いていた囃子の音などを覚えており、なんとか踊りを復活させられないかと、寺尾や深谷に住んでいる人たちや、寺尾から別の地域に嫁いでいった人たちを訪ね歩き、唄や踊りについての情報を集めました。さらに、別の地域のささら踊りなども調べ、その踊り方を参考にして、綾瀬のささら踊りを復元したのです。このときに、神奈川県教育委員会の指導を受けて、ささらを使って踊る盆踊りを総称して「ささら踊り」と呼ぶことにしました。
その後、復元した綾瀬のささら踊りを広く周知して、次世代に継承するために「綾瀬ささら踊り保存会」を作りました。
(註※1 しょうは、昇の異体字。日に舛)
(参考:2001『綾瀬市史8(下) 別編 民俗』綾瀬市)
綾瀬ささら踊り保存会

綾瀬ささら踊り保存会の踊りの様子
綾瀬ささら踊り保存会は、ささら踊りを伝承し、未来へ伝えていくことを目的として、昭和51年(1976)8月1日に結成されました。
平成初期から中頃までは綾瀬市内の各小学校に教えに行っており、運動会などでも踊られていました。近年は小学校からの依頼で授業に赴いたり、市内の複数の保育園に教えに行くなど、次世代へ伝える活動に力を入れています。また、市民文化祭 伝統芸能部門や公民館祭り、各イベントなどに出演し、ささら踊りの普及啓発を行っています。
相模ささら踊り

相模ささら踊り大会の様子
神奈川県の相模川周辺から足柄地域にかけては、類似した踊りが広く踊られていたことが確認されています。
ささら踊りは、昭和29年(1954)頃に南足柄市で結成された保存会に続き、県内各地で復活・保存会の結成が行われました。そのような状況の中、神奈川県教育委員会の指導のもと、昭和51年(1976)に県内各地のささら踊りの保存会が集い「相模ささら踊り連合会」が結成されました。
相模ささら踊り連合会は、6市8団体(現在1団体は休会中)で構成されています。毎年7月に「相模ささら踊り大会」を実施しています。各地のささら踊りが一堂に会するため、地域ごとの踊りや唄の違いを見ることができます。
着物を着てタスキを掛けた踊り手の方々が大きな円を作って綾瀬ささらおどりを踊っている様子の写真 拡大画像 (JPEG: 23.7KB)
第46回相模ささら踊り大会に出演しました!

綾瀬ささら踊りの様子
令和6年7月24日に厚木市荻野運動公園メインアリーナにて行われた、第46回相模ささら踊り大会に出演しました。
相模ささら踊りの普及・啓発・継承のために、各保存会が集い、各地のささら踊りを披露しました。
令和7年の相模ささら踊り大会は、藤沢市で行われる予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


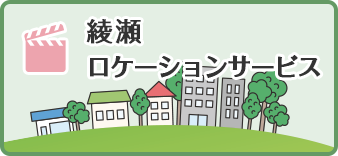
更新日:2024年08月24日