市指定文化財17 道場窪遺跡出土縄文時代中期の土器・石器等一括
市指定文化財 道場窪遺跡出土縄文時代中期の土器・石器等一括

道場窪遺跡・道場窪遺跡出土土器
道場窪遺跡からは、土器や土製品、石器や石製品など数多くの遺物が出土しました。出土した遺物の時期は、旧石器時代、縄文時代中期から縄文時代後期前半にわたります。
多くの出土遺物の中で、縄文時代中期の環状集落を語るうえで欠かすことができない、‟縄文時代中期”の土器・石器などをまとめて、令和6年3月12日に市の指定文化財に指定しました。
※HPに掲載されている写真を使いたい場合は、必ず生涯学習課市史文化財担当へ申請してから使用してください。

市内最大の土器(曽利式土器:69.8センチ)
指定した土器・石器等の総数【908点】
~内訳~
・縄文土器 計233点
・土製品 計181点
(土製品:土錘、土製円盤、焼成粘土塊)
・石器 計492点
(石器:石鏃、石錐、石匙、削器、掻器、 剥片、石核、礫器、石錘、凹石、敲石、砥石、台石、石皿、楔形石器、打製石斧、磨製石斧、磨石、その他石器)
・石製品 計2点
(石製品:大珠、線刻礫)
特徴

道場窪遺跡出土土器(一部)
【土器】
勝坂式土器・加曽利E式土器・曽利式土器が中心に出土します。縄文時代中期中葉から後葉にかけての各時期の資料が豊富であることから、本遺跡の継続期間や時期ごとの変遷が分かるため、集落内での人々の暮らしを検討することができます。

道場窪遺跡出土 石錘(せきすい)、磨石
【石器】
石鏃(せきぞく)や石錘(せきすい)などの狩猟に関する道具や、石皿・磨石などの食べ物の加工に関する道具、打製石斧や磨製石斧など暮らしに係る道具など、幅広い種類の石器が出土しています。
特に、石錘が遺構の内外からたくさん出土していることから、目久尻川を使って河川漁労をしていた可能性が指摘されています。
道場窪遺跡出土の石器は、縄文時代中期の内陸における生活や生業、文化を紐解くことができる重要な資料です。

左:黒曜石製の石鏃、右:ヒスイ製の大珠(たいしゅ)
【交流のわかる遺物】
道場窪遺跡から出土する土器や石器の中には、綾瀬周辺では作られていない土器や採取できない石材を使用した石器があります。これらの土器や石器を調べることで、縄文時代の綾瀬の人々がどの地域の人々と交流があったのか、当時どのような物流があったのか考えることができます。
これらの遺物は、縄文時代中期の地域の歴史を知る上で欠かすことができない重要な出土遺物です。
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


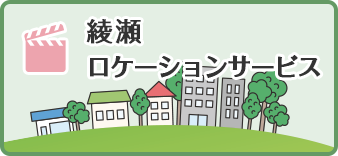
更新日:2024年10月01日