令和7年度第1回綾瀬市生涯学習推進審議会(令和7年7月10日開催)
審議会等の名称
令和7年度第1回綾瀬市生涯学習推進審議会
開催日時
令和7年7月10日(木曜日)午後1時30分から午後3時まで
開催場所
綾瀬市役所 事務棟6階 J6-1会議室
議題
(1)生涯学習推進プランの進行管理について
出席者
委員
- (会長)見上一幸
- 白井哲哉
- 佐藤和美
- 古賀陽子
- 山内敏子
- 米島美穂子
- 深澤利彰
- 橘川純子
事務局等
市民環境部長 他7名
傍聴者数
0名
内容
内容は、要点報告です。
会長:議題(1)「生涯学習推進プランの進行管理について」事務局より説明をお願いします。
事務局:(議題(1)「生涯学習推進プランの進行管理について」説明。)
会長:説明ありがとうございました。生涯学習推進プランの重点取組である「読書活動の推進」について、委員の皆様から御意見を伺いたいですが、いかがでしょうか。
委員:生涯学習推進プランに記載のある事業に参加された、お子さんや保護者の方からは、どのような声が寄せられましたか。
事務局:利用者の皆様からの御意見や御感想については、各事業を実施している図書館に寄せられております。また、月に1回、実施をしております図書館と生涯学習課での情報交換の会議の場では、利用者の皆様からの御意見等について適宜情報共有を行っております。そのほか、図書館から生涯学習課に毎月提出される業務報告書を通じて、利用者の皆様からの御感想やお声について把握をしております。「図書館のサービスが拡大したことで、図書館へ行くことが楽しくなった」などのお声をいただいたこともございました。また、親子で参加できる英語の絵本のイベントでは、保護者の方同士の交流が見られたことや、イベント参加後はそのまま図書館で本を借りて帰られる親子連れの姿も見受けられ、事業の主となる目的を果たすだけでなく、事業実施にあたっては副次的な効果もあるようでございます。毎月の子育て支援センターの絵本の読み聞かせ講座でも、保護者の方同士の交流があるほか、保護者の方も自分のお子さんの反応を見ながら、講座内容を読書活動へ役立てていただいているようでございます。
委員:承知しました。ありがとうございます。
会長:ほかに御質問等はいかがでしょうか。
委員:綾瀬市子ども読書活動推進計画の対象年齢を教えてください。また、セカンドブック事業の終了の理由を教えてください。
事務局:綾瀬市子ども読書活動推進計画の対象年齢は18歳以下でございます。また、セカンドブック事業については、あやせゼロの日運動の事業の一環として実施をしてまいりました。事業内容といたしましては、新小学校1年生全員に図書館の司書が選んだおすすめの本、全5冊の中から気に入った1冊の本をプレゼントするというものでございました。事業が終了する理由は、先ほどの御説明のとおり、市の総合的な政策判断によるものでございます。詳細にお話をしますと、本市の教育委員会において、学校図書館を充実させる方向性を軸とし、事業の強化年度として令和4年度から令和6年度にかけて予算を増やし、倍の冊数の本を購入したことや、全国的な課題として学校図書館の人員不足が挙げられますが、綾瀬市は学校司書を各学校につき1人ずつ配置し、児童生徒が在校している時間にあわせて学校司書の勤務時間を調整し、子どもたちの読書環境の整備を図ったほか、学校図書館のシステムの整備を強化するなど、学校図書館の全体としての環境を充実させてまいりました。その経過も踏まえまして、一人ひとりに本を配る事業より児童生徒が集まる学校図書館の読書環境を充実させた方が高い費用対効果があることから、集合型の学校図書館に力を入れていく方向にシフトするという市全体の考えを踏まえ、セカンドブック事業は終了となりました。
委員:いただきましたお話から、現在の綾瀬市では、学校司書が各学校に1人は配置されているという認識で間違いないでしょうか。また、セカンドブック事業の終了の理由については、市の総合的な政策判断に基づいて、予算の充当部分に変更があったということで合っていますか。
事務局:はい。合っております。
委員:各学校の学校図書館に学校司書が必ず配置されていることはとても良いことだと思います。また、会議資料にも記載されていますが、市立図書館などでは乳幼児向けのイベントやおはなし会、英語を使ったイベントなどが充実している印象ですが、小学生、中学生、高校生向けに人が密に関わっていく事業はありますでしょうか。
事務局:学校連携という点では、図書館の活用方法について内容をまとめた資料を各学校に配布しており、学校の先生方へ図書館からのプッシュ型で情報発信を行っております。また、学校の授業内容にあわせた本の貸出や、学校図書館に希望の本がない場合に、その本を図書館が持っていれば学校へ貸し出すことも実施してございます。そのほか、図書館や本に親しみをもってもらうために、図書館の見学イベントの実施や、学校司書の図書館運営のサポートとして、市立図書館の司書が学校に出向き、展示コーナー作成のアドバイスや必要に応じて運営支援の助言を行うことも実施しております。また、学校司書が一堂に会する会議に市立図書館司書も出席し、図書館の電子図書館サービスの案内など、様々な部分で学校に向けての情報共有、情報提供に努めております。また、近年では「読書離れ」などという言葉のとおり、読書をする時間が減っているのではなく、「そもそも本を読まない」「本を手に取らない」ことが増えております。そのような中で、読書をすることに対して「本」からのアプローチではなく、異なる切り口からのアプローチを図書館では行っております。例として、マジパンづくりなどの講座を開き、参加者には実際に図書館の本を見ながら作業をしてもらったり、会場内に講座の内容と関係のある本を展示したりしております。「本」への切り口は講座ですが、結果として本とつながりをもつことができる事業をお子さん向けに実施しております。
委員:今後、綾瀬市子ども読書活動推進計画を改定されるということで、全国的に本から離れてしまっている傾向を踏まえ、「本を読むと楽しい」「本を読むと豊かになる」ということを伝えていけるようなソフト面でのアプローチがあると良いと思いました。
事務局:貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。
会長:現代においては、子どもたちの「探求」が非常に盛んになってきています。子どもたちが自分のテーマを探るときに、本に頼る、本から解を探していくという一つのアプローチも重要だと思いました。自分自身も地元の幼稚園の運営等に関わっていますが、月に数十冊ほど市立図書館から配本サービスを提供いただいております。提供いただく本の中には、幼稚園の先生が普段、自分では買わないような面白い本が入っていることがたまにあるそうです。また、ある中学校の先生からは、最近、子どもたちの読書時間が伸びているというお話を伺いました。ただ、本を読む時間は伸びたものの、本の内容をどれだけ学びとっているのかについては十分ではない部分があるようで、もう少し仕掛けのようなものが必要だと思いました。「ただ本を読めば良い」というわけではなく、中学生や高校生になれば、ビブリオバトルといった、自分が読んだ本の面白いと思った部分をクラスメートや友人の前で話をする、またそれらをお互いに話し合うということも大事ではないかと思います。幼稚園や保育園などの低学年の子どもたちには、単なる読み聞かせではなくて、子どもたちからの問いを引き出し、それに対してやり取りをしながら絵本を読ませるというのも新しい形だと思います。本を使って物事を考える、そんな仕掛けがさらにできるとよいと思いました。
事務局:貴重な御意見ありがとうございます。関係各課にも情報共有させていただきたいと思います。
委員:先ほどの説明の中で、学校司書が不足しているとのお話がありましたが、詳細について教えてください。
事務局:人材不足というよりは各自治体の予算不足が原因で、全国的に学校1校につき、学校司書を1人配置することが難しい状況にあります。常に学校側は様々な課題があり、限られた学校教育予算の中で、なかなか学校図書館に予算を割くことが難しいという課題が全国的にございます。
会長:市民のボランティアを活用することも良いと思います。
委員:中学校の図書ボランティアを長年務めていますが、以前は学校司書の数も十分ではなく、図書委員も放課後は部活動があり図書館にいることができないため、お昼休みしか図書館を開けることができないといった状況もあり、それではあまりにも図書館から生徒の足が遠のいてしまうと思い、図書ボランティアを始めました。最近ではボランティアの数も少なくなってきましたので、自分自身もボランティアを辞めても良いかと思っていた部分もありましたが、学校側から継続してほしいというお話をいただき、週に1回の活動を現在も続けております。先週も学校司書の方が急病になってしまい、代理でボランティアに入れないかという話を学校からもらいましたので、協力をさせていただきました。長年にわたり、この活動を続けてまいりましたが、学校司書の方がいらっしゃるおかげで、以前とは違い、子どもたちの足が向きたくなるような図書館になったと思います。ボランティアだけでは貸出業務や本の整理で精一杯な部分がありましたが、学校司書の方のおかげで図書館が楽しい場所になったと感じております。学校司書の方は、学校の先生も巻き込んで、先生方のおすすめ本の本棚を作ってくださり、その他にも学校司書の方が取り組んでくださるものは毎回、魅力的なものが多いと感じております。図書室は校内の一番奥に位置しており、寂しい印象でしたが、学校司書の方のおかげで最近は生徒の皆さんから人気がある場所に見えています。自分自身、保育ボランティアとしても活動していますが、平日の昼間に、お父さんとお子さんが参加されている姿も目にしており、1年に数回ほど、休日にお父さんとお子さんが本にふれることができるイベントなどがあると良いと思いました。
事務局:図書館にて、様々な親子向けのイベントを実施していますが、参加される方々の中心はお母さんになっていることを踏まえ、お父さんが中心に参加できる場も用意した方が新しい展開ができるのではないかという趣旨のお話になりますでしょうか。
委員:そうです。
事務局:貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。図書館側にも情報共有させていただきたいと思います。学校図書館のボランティアのお話については、長い間御尽力くださりありがとうございます。自分自身、別の業務で市内の学校へ出向くことがございますが、そのたびに学校図書館に行くのが楽しいと感じております。本のポップや充実した特集コーナーなど、各学校の学校司書の皆様が色々と工夫を施してくださり、素晴らしいと感じております。
委員:学校司書の方の生徒への指導の仕方も素晴らしく、大変良いと感じております。
事務局:御意見等ありがとうございます。関係各課にも情報共有させていただきたいと思います。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:ないようですので、引き続き、重点取組以外の事業について、何か御質問等はありますか。
委員:あやせゼロの日運動に関して、意見が一つあります。ゼロが付く日には、運動の呼びかけとして、市内の防災無線を使い、運動の周知や取組の啓発内容を放送していることと思います。現在の放送時間について、夜の時間帯に流していらっしゃるかと思いますが、ゼロが付く日の前の日に流した方が効果的だと思います。ゼロが付く日の夜の時間帯に流しても、その日の活動はすでに終わってしまっているかと思います。
事務局:貴重な御意見をいただきましてありがとうございます。放送時間については、令和4年度まではゼロが付く日の朝の時間帯に流すようにしていましたが、共働き家庭や忙しい朝の時間帯に放送を聞いても頭に残らない、また、帰宅する頃には放送を聞いたことを忘れているという御意見もあり、社会教育委員の皆様に相談し調整を図りました。また、学校側の意見として小中校長会からも同様の意見等をもらい、令和5年度から、より効果的な時間帯として、放送時間を家族の団らんが始まる時間、家族が集まって夕食が始まるような夜の時間帯へ移行させていただきました。また、保護者の皆様からも、同じような御意見をいただいたことも、時間変更の理由の一つでございます。これらの経緯等を踏まえまして、現状の対応については御理解をいただけますと幸いでございます。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:他に御意見等はないようですので、議題(1)「生涯学習推進プランの進行管理について」は以上といたします。次に情報交換にうつります。それでは情報交換(1)「あやせ目久尻川歴史文化ゾーン構想の推進について」事務局より説明をお願いします。
事務局:(情報交換(1)「あやせ目久尻川歴史文化ゾーン構想の推進について」説明。)
会長:事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何か御質問等はございますか。
会長:綾瀬西高校との連携のお話がありましたが、よくある学校連携の形として、高校生が小中学校へ出向き、自分で調べたことを発表するといったことがありますが、そのようなことを実施する予定はございますか。
事務局:そのようなお話について、今のところ予定はございませんが、あやせ目久尻川歴史文化ゾーン構想の推進にあたり御協力をいただいております、委員の綾瀬西高校の先生からは「高校生だけでなく地域の人々との連携を大事にしながら、小さな子どもたちにも目久尻川の魅力や素晴らしさを伝えていきたい」とお話を伺いました。行政だけでなく、高校生の皆さんとも積極的につながりをもつことができると良いと考えております。
会長:ありがとうございます。他に御意見や御質問はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:他に御意見等はないようですので、情報交換(1)については以上といたします。次に情報交換(2)「生涯学習推進プラン後期実行計画の策定について」事務局より説明をお願いします。
事務局:(情報交換(2)「生涯学習推進プラン後期実行計画の策定について」説明。)
会長:事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何か御質問等はございますか。
委員:「地域学校協働活動」について詳しく教えていただきたいです。
事務局:綾瀬市では地域学校協働活動推進員を「地域コーディネーター」と呼び、市立の小中学校の全校に配置しております。例えば、地域コーディネーターは学校運営協議会における議論で学校が補助やサポートとして地域の人々に協力を求めた際、地域と学校との間に入り調整を行います。地域学校協働活動は、より良い学校づくりに地域の方々も参加し取り組むという側面と、反対に、地域での課題に学校側に協力を求め地域づくりに関わり取り組むという側面がございます。コミュニティ・スクールや地域学校協働活動については、綾瀬市でも活発化してきているという現状でございます。
会長:コミュニティ・スクールとは従来の学校よりも地域性を持たせ、地域の人たちが学校運営に関わる責任を持つと理解しております。小中学校の全校においてそのような動きがあり、地域全体が学校を支える形、また学校も地域全体を支える形ということで、地域学校協働活動が生まれるものと認識しております。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:部活動の地域展開のお話があったと思います。内容について詳しく教えてください。
事務局:今まで学校の先生が教えていた学校の部活動について、先生に代わって地域の人々が教える役割を担う形を進めていくという文部科学省の方針がございます。綾瀬市もその方針のもと、令和8年の夏頃から、休日の部活動は地域クラブに移行していく方向性で関係各所と調整を進めております。なお、平日の部活動については、当面の間は学校部活動として残る形となります。部活動の地域展開については、生涯学習推進プランの後期実行計画に新たに内容を記載する予定でございます。
委員:承知しました。ありがとうございます。
会長:綾瀬市が生涯学習都市宣言をしたのはいつでしょうか。
事務局:平成6年です。
会長:生涯学習都市宣言と、この生涯学習推進プランについて何か関連はありますでしょうか。
事務局:生涯学習推進プランの基本方針の冒頭、すなわち計画の核となる部分に記載してございます。
会長:生涯学習都市宣言していることを、このような審議会の場を含め周知していくことで、より綾瀬市の特徴が出てくるものだと思います。
事務局:貴重な御意見いただきましてありがとうございます。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:他に御意見等はないようですので、情報交換(2)については以上といたします。次に情報交換(3)「第4次綾瀬市子ども読書活動推進計画の策定について」事務局より説明をお願いいたします。
事務局:(情報交換(3)「第4次綾瀬市子ども読書活動推進計画の策定について」説明。)
会長:事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何か御質問等はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:御意見等はないようですので、情報交換(3)については以上といたします。次に情報交換(4)「公共施設再編事業について」事務局から説明をお願いいたします。
事務局:(情報交換(4)「公共施設再編事業について」説明。)
会長:事務局の説明が終わりました。委員の皆様から何か御質問等はございますか。
委員:北の台地区センターが休館していますが、地区センターやコミュニティセンターはどのような方々が利用されていますか。
事務局:様々な団体の皆様に御利用をいただいておりますが、広い部屋ですと体操やダンスといった体を動かすような目的で御利用いただいている場合が多いです。
委員:北の台地区センターに限らず、他の建物を含め、建て替え後の新しい施設においては、以前に利用していた団体の皆様にも引き続き御利用いただく形を想定していますか。
事務局:そのような想定をしております。
委員:旧北の台地区センターについて、施設の建て替え後は、利用料金が少し値上がるのが気になりました。また、建て替え後の「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」内の「多目的交流室」は2つの部屋に分けて使用することはできますか。
事務局:「多目的交流室」は2つの部屋に分けて使用することはできません。
委員:「多目的交流室」はフローリングの仕様で、卓球などはできますか。
事務局:旧北の台地区センターの第1会議室という部屋には卓球台がありましたので、「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の「多目的交流室」でも、卓球台を引き続き御利用していただくことを想定しております。
委員:早園地区センターの場合には、大きな部屋を2つに分けて貸すという話があったと思うのですが、「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の「多目的交流室」は部屋が広いにも関わらず、2つの部屋に分けることができないのは驚きました。卓球をされる方も多いと思いますので、これだけ広い部屋を1グループで使用するというのは、あまり聞かない話だと思います。「多目的交流室」を2つの部屋に分けての運用することについての配慮や考慮といった意見などはなかったのでしょうか。
事務局:旧早園地区センターは63平米の部屋が複数ありましたので、建て替え後の新しい施設でもその面積を維持しつつ、2つの部屋をつなげて使用できると良いという点も含めまして、早園地区センターは元々の部屋の面積を活かした形で、建て替え予定でございます。新しい「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の「多目的交流室」においても、旧北の台地区センターの第1会議室の広さを極力維持するような形にいたしました。「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の「多目的交流室」については、市の公共施設の利用料金を決める基準がございまして、本来であれば950円を上回る料金となりますが、基準に従って激変緩和措置として、料金を抑えた上で950円と設定しております。ただ、利用者の方には、丁寧な御説明が必要であると考えております。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の「文化活動室」というのは防音の仕様になっていますでしょうか。
事務局:防音の仕様になっております。
委員:楽器の練習なども行うことができる想定でしょうか。
事務局:楽器練習の御利用も想定してございます。ただ、どの程度まで楽器の音が隣の部屋に響いてしまうのかなどは、運用してからでないと分からない部分もございます。
委員:金管楽器は音がよく響きますので、練習での利用は難しい場合があるかもしれません。
会長:防音仕様の基準はどのくらいでしょうか。
事務局:防音壁自体はマイナス30デシベルでございます。この「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の建物自体のコンクリートの厚みは15センチであり、このコンクリート壁自体も防音効果がありますので、総じてより高い防音性能があるものと認識をしております。プロの設計士の方により、音楽活動を行ってもある程度は耐えられる防音仕様として部屋は設計いただいておりますので、大きな影響や問題はないと考えております。ただ、どこまで防音ができるかという部分については、数字上で図れる部分と実際に運用してみないと分からない部分もあるかと思います。また、「会議室」と「文化活動室」はある程度距離がありますので、音の大きさによる影響はないかもしれませんが、「多目的交流室」と「文化活動室」は隣り合っていますので、複数の楽器が重なったりする練習をした際には、影響が出てしまうこともあるかもしれませんが、そのような場合には、実際の運用を進めながら十分な調整を図ってまいります。
委員:「文化活動室」のドアは何重でしょうか。
事務局:一重です。
委員:一重では音漏れのない完全な防音というのは難しいかもしれません。
事務局:「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の建物自体は音楽専用の施設ではなく、社会教育施設でありますので、完璧な防音対策がなされた設計を行うのは難しい部分もございます。
委員:「文化活動室」については、どのような団体にご利用をいただくイメージでしょうか。声楽や合唱の団体の利用を想定されていますか。
事務局:そのような団体の方々を想定しております。また、「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」は地区センターとしての機能を持ちながら、自治会館機能である「蓼川自治会館」とあわせた施設として運用予定でございますので、「蓼川自治会館」にて高齢者憩の家で、高齢者の方が毎週カラオケをやっていらっしゃったことも考慮し、継続してその活動ができるよう、「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の「文化活動室」はカラオケをすることも配慮された設計となっております。
委員:会議資料に記載のある「綾瀬市立中央公民館北の台コミュニティプラザ」の説明部分ですが、建物の設計図を表している2つの図については、建物の1階と2階を指すものでしょうか。双方を見比べると縮尺が異なるように見えますので、少し見づらさがあり、2つの図のつながりが少し分かりづらく感じます。
事務局:おっしゃるとおり、若干ですが、縮尺は異なっております。2つの図でそれぞれ1階と2階を表したものであり、一つの建物の説明となってございます。
委員:分かりました。ありがとうございます。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:他に御質問はないようですので、情報交換(4)については以上でございます。次に情報交換(5)「その他」について事務局より御説明をお願いいたします。
事務局:(情報交換(5)「その他」について説明。)
委員:生涯学習推進プランの後期実行計画の策定にあたり、審議会の実施回数が予定よりも増えるのであれば、いつ頃の実施を予定していますか。
事務局:11月か12月中の追加実施を予定してございます。
委員:承知しました。
会長:他に御意見や御質問はございますか。
委員:(意見・質問なし)
会長:ないようですので、 本日予定しました議題はすべて終了いたしました。
事務局にて閉会。
以 上
この記事に関するお問い合わせ先
- 綾瀬市ホームページをより使いやすくするために、皆様の声をお聞かせください。
-


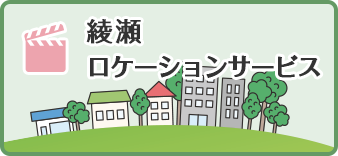
更新日:2025年08月01日